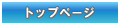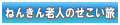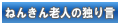徐福考
中学のころ、誰もがそうであったように、私もピラミッドとか万里の長城とかいうものに強く惹かれました。当
然秦の始皇帝という人物についても興味をもち、伝記のようなものを読み漁ってひとかどの歴史学者にでも
なったような気分でいたのは、今から思うと汗顔の至りながら懐かしい思いもします。
その後少しずつ読みかじり聞きかじりしているうちに、徐福という謎めいた方士の存在を知り、怠惰な私と
しては珍しく真面目に調べたりしました。
しかし、調べれば調べるほど違った伝承が見つかり、いったい何が事実で何が後世の脚色なのか分から
なくなってきたのも事実です。
そこで、私の中の徐福像をいったん整理するために、手持ちの資料の中から繋がりのありそうなものだけ
を選び、食い違うものや矛盾するものを躊躇わずに捨てて、自分だけの勝手な 『徐福伝』を作ってみたの
がこの稿です。
伝承と伝承の間を私の推測で埋めたり、「歴史」には登場しない市井の人々のことを想像で書いたりして
いますので、およそ非学問的な「お話」でしかありませんが、それを承知でお読みいただけたら、 こんなに
嬉しいことはありません。
暴君からの壮大な脱出劇
時は紀元前221年、斉の琅邪(ろうや)に徐福という、50の半ばを少し過ぎた方士がいた。
方士といえば薬学、占星術、天文学等に精通した学者であるが、近頃では怪しげな呪術師、祈祷師などが自らを方士と名乗り始めたこともあり、その評判は必ずしも高いものではない。
むろん知徳相備えた真の方士もまだまだ多く、徐福もその一人であった。村民の信望も厚く、いわば村の名士といった存在の徐福は、妻と4人の子供に囲まれて何不自由のない生活を送っていた。
 |
| 徐福像・新宮市徐福公園 |
長く続いた春秋戦国時代には、魏・楚・斉など七雄と呼ばれる国々が覇を競ってきた。それらが巧まずして均衡を保ってきたおかげで、大きな戦もなく、多くを望まぬ限り民の暮らしは比較的落ち着いたものであった。
そのままであれば、徐福も地方の名士として平和な人生を終えていたであろう。
しかし、時代は一家にとって悪しき方向へ流れ始めていた。
急激に力をつけた秦がにわかに強大な軍事力を背景に他を圧するようになり、七雄の均衡が危うくなってきたのである。国々は秦との正面衝突は避けながらも、事実上秦の顔色を窺わずには国の存立を維持できない状況追い込まれた。
加えて、王権を巡る権謀術数の果てに13歳で王位についた政が成長とともに力をつけ、側近を排して親政に踏み切ると、非情な粛清を繰り返して絶対君主の地位を築き、領土拡大に血道を上げ始めた。
政が名実ともに中国全土を統一する日は近い、という話が徐福の住む琅邪にも聞こえてきた。
政王は度量衡の統一を始めとする優れた為政で国力を増大させ、その政治力は抜きん出ていたが、半面、容赦ない武断政治で人心を遠ざけてもいた。
このこと自体は、一人の独裁者が全土を支配する政治形態、すなわち“帝国”の持つ宿命であり、仕方がないともいえる。
帝国というのは、中央集権の極まった姿であり、すべての権力が一人の人間、すなわち“帝”に握られている政治形態である。ということは、その独裁者さえ倒せばその国を奪えるということであり、その機会を窺う者は国の内外に絶えることがない。
いきおい権力者は疑心暗鬼になり、必然的に武断政治に走る。政王ならずとも人を信じていては政治は行えない。
ではあるが、政王はいささか度が過ぎた。
それまで各国の支配者は王と呼ばれていたが、政はそれに満足しなかった。神話時代に「皇」と呼ばれた聖人が3人、「帝」と呼ばれた聖人が5人いたという話を聞き、ならば自分はそれらをしのぐ者であるという意味で「皇帝」という称号を考え出した。
のちの支配者たちがこぞってそれを真似、皇帝、皇帝と名乗ったものだから政はその始めということで「始皇帝」と呼ばれるようになる。
そこまではにわかに権力を得た者にありがちな悲しい自己顕示欲といって笑うこともできるが、ためを思って進言する忠臣をことごとく処断した異常な猜疑心は、独裁者の孤独を語って憐れでさえある。(注1)
政権が交代すると、新政権はしばしば前政権の建造物をヒステリックなまでに破壊する。政もそれはいやというほど見てきた。我が秦だけが例外である筈がない。現に国内にも反乱というほどではないものの小さな離反はいくつか見られ、都度、過剰なまでの武力を投じて潰してきた。
我を取り巻くすべての者を信じられず、意に反する者には力を以って当たる。行き着くところは恐怖政治。これもまた歴史の必然ではあるが、専制政治も恐怖政治も自分の命あってのこと。
死ねば、たちまちにして周辺諸国、いや身内の側近までもが雪崩を打って攻め込んでくることは火を見るより明らかである。居城の破壊はもとより、墓までも暴かれ、始皇帝の生きた証は完膚なきまでに消滅させられるであろう。
始皇帝は、人心我にあらずということを十二分に自覚していた。そもそも人の心を信じるという余裕などなかった。
死ねば、領土も栄光も踏みにじられる。力のみで他を圧してきた自分が、死後にどのような扱いを受けるかは、目に見えている。
人心の離反や相次ぐ反乱の兆しに、始皇帝は自分の首が市中に晒される光景を思って戦慄した。そうして眠れぬ夜を重ねた挙句、自分がそういう仕打ちを受けぬためには自分が死なないことが唯一の方法であるという子供じみた思いに至る。
そしてなんと、不老不死を図って大真面目に手を打ち始める。呪術師に祈祷させるという古典的なやり方は無論のこと、自らも霊山に登って天に祈る。さらに各地の方士たちに命じて不老不死の仙薬を探させるという、正気とは思えぬ策に走った。
方士として評判の高い徐福が呼び出されるのは時間の問題であり、その時はきた。
「不老不死の仙薬を求めてまいれ」
始皇帝の命令は絶対であった。そんなものがあるわけはございません。誰しもそう言いたい。しかし、それを言うことは自分の死を意味する。
命令を受けた方士たちは国の内外に散った。空手で帰る方士たちは考え得る限りの言い訳をし、激怒する始皇帝に追われるようにまた探索の旅に出る。
徐福もまた同じであった。
始皇帝が斉を滅ぼして中国全土を統一したその2年後、徐福は薬の探索を命じられる。徐福は、不死はともかく、せめて不老の薬を得ようと懸命の旅を続け、9年後、空しく帰京する。当然、なんら成果を示せぬ自分の身が極めて危ういことを思い、どう言い逃れるかを考え続けた。
思いつく言い訳はどれも始皇帝の納得を得られそうにない。よしんば一度は切り抜けたとしても、次に帰るとき、2度の不首尾を始皇帝が許す筈はない。そのときこそ身の終わりだということは考えるまでもない。
考え抜いた挙句に徐福がついた嘘は驚くべきものであった。
「東海の彼方に蓬莱という神山があり、仙人が住んでおります。今回は鯨に阻まれて辿り着けませんでしたが、聞けば良家の童男童女と様々な分野の技術者を献上すれば仙薬を取らせると言っています。必要な人材と費用をお預け頂ければ再度出向き、必ずや不老不死の薬を手に入れてまいります」
不老不死の妙薬という荒唐無稽な話を否定するどころか、さもありそうに述べて始皇帝の気を引き、“必ず”それを持ち帰ると断言すれば、とりあえずは命を取られることはなかろう。しかし、薬を持ち帰ることはもとより不可能である。またしてもおめおめと手ぶらで帰ったのでは許される筈はない。
そう。徐福は、帰るつもりはなかった。
海のかなた、余人の追ってこられぬ島国に渡って、そこで暮らそうという腹である。しかしその困難は計り知れない。
まず海を渡る術がない。船の建造には莫大な資金と技術が要る。操船には船乗りも雇わねばならぬ。長い航海に必要な水、食料、衣類の確保、調理や雑用の人手。
首尾よく島に辿り着いたとして、まず言葉が通じまい。信仰も習慣も違う社会の中でどう生活していくのか。
考えられる方策はただ一つ。何千人という仲間で一挙に移民し、まずは異国に中国人社会を作ってしまうことである。土地の人との融和はそれからでよい。
徐福はそれらの膨大な資金と技術者、仲間をすべて蓬莱に住む仙人への手土産として始皇帝からせしめるという、とてつもない賭けに出たのである。
典型的な専制君主であり、人心掌握ままならず、権力だけが拠り所の支配者というものは、しばしば常人の理性を失っていることがある。そもそも自らの不死を図ろうという時点で既に始皇帝の判断力は狂っている。
そんな始皇帝に、徐福の“はったり”を見抜く力はない。
始皇帝はまんまと徐福の言にはまった。若い男女3千人を徐福に預け、それを運ぶ船を建造させた。30人乗りの船としても百隻。船乗り、船大工、料理人も乗せることを考えればさらに大きな船か、さらに多くの船が必要になる。(注2)
徐福はまた、蓬莱への献上品と称して様々な穀物の種を用意させた。獲得した新領地に耕作者を集団で定住させる屯田は戦国の常套手段であり、徐福はそれを蓬莱で行おうとしたのである。
かく、用意周到な徐福であったが、降って湧いた災難を嘆いたのは、蓬莱行きを命じられた庶民である。
徐福は異郷に住み着くために必要な人員、わけても知識人、技術者を、仙薬の対価と称して始皇帝に用意させた。
3千人に上る若い男女。たまたま選ばれたために恋人と引き裂かれた者もいた。病気の親を残さねばならぬ者もいた。百隻もの船に乗り込む大勢の船乗り。荒海での航海となれば船の損傷もあろうから船大工も同行しなければならぬ。船中での料理にあたる人々、病人に対処する医者、かの地での屯田を指導する農業技術者、農具や武器を作る鍛冶、衣類を作る機織り、等々。
始皇帝は各地に官吏を走らせ、人員を集めた。
3千人の若い男女は、はなから蓬莱国への捧げものであり、その地で一生を終えることが命じられる。年頃の息子や娘を持つ親たちは慌てふためき、中には娘を山中の知人に預けて役人には娘が既に死んでいると言い張る親もいた。それが成功したのは、役人に賄賂を渡せる恵まれた家だけであり、貧しい者は親が病気であろうと年寄りであろうと、容赦はされなかった。
蓬莱を豊かな先進国と考え、あるいはそうではないにせよ、今自分が住んでいる所よりはましな所だろうと考えて、積極的に渡航を承知した若者もいなかったわけではないが、それは極めて限られた数である。
知識人、技術者は、それなりに生活が安定している。それを捨てて見知らぬ国に移住する理由がない。そういう人たちについては、役人も気を使った。
なにもかの地に永住するわけではない。ある期間そこで人々に知識、技術を教え、成果を上げた上で帰ってくればいい。そう言いくるめた。
船大工、船乗りについては、ただ蓬莱の仙人に献上する人と品を運ぶだけで、それが済んだら直ちに引き返すのだと話してある。これはまんざら嘘ではなく、始皇帝も船乗りたちは徐福とともに不老不死の薬を積んで帰ってくるものと思っていた。
すべてを知っていたのは徐福のみである。
秦はもともと戦国の七雄の中で最も西の小国であった。始皇帝自身も即位後の巡幸までは海を見たことがなかったくらいで、秦に造船の技術はない。
造船は秦に併合された斉と楚の船大工を動員して行われ、出航は楚の港町寧波と決した。そこに人員がすべて結集し、いよいよ出航の日が近づいたころ、徐福は同行者のうち、最も信頼できる7人にだけ、真の計画を打ち明けた。
7人の驚きようは一通りではない。もとより帰還の保証されない危険な旅であり、家族とは今生の別れと思ってそれなりの言葉を残してもきた。しかし、首尾よく帰還できれば地位も身分も数段格上げされ、家族の生活も向上するであろうという期待は大きかった。
それを、いきなり二度と帰らぬと宣言されて動揺しない者はいないであろう。
徐福は頭を下げ、身勝手な計画を詫び、胸中を赤裸々に語った。
仙薬探索の旅は自分が望んでするのではない。断れる命令でないことは諸氏も承知の通りだ。しかもそのような薬を持ち帰ることはできる筈もない。帰ったときには私はもとより、諸氏に対しても厳しい咎めが待っている。
生き残る道はただ一つ。帰らぬことだ。
7人とてもそれは分かる。しかし、それならもっと早く言ってくれれば家族を連れてくることもできたのに。恨み混じりの言葉が続いた。
最後まで聞いた徐福は言った。自分も家族に黙って出てきた。妻子を同行させたのでは怪しまれる。といって、妻子に打ち明けて動転されたのでは、秘密の保持も危うくなる。怪しまれず、騒ぎにならず連れて出られるぎりぎりの線として、徐福は4人の息子のうち、次男だけを連れてきていた。
それを聞いて、7人は腹を決めた。権力を振り回して臣民を追い詰める暴君のもとで日々戦々恐々と生きるより、言葉も通じぬ異郷での苦労の方がマシというものかも知れぬ。
実は徐福には、旅立ちにあたって親族を集めて言い残したことがある。
仙薬探索の旅に出るが、必ずしも成功は望めない。不首尾であれば皇帝は徐一族を厳しく処断するに違いない。ついてはこれより先、徐姓を捨て、私との関係を隠し通すように。(注3)
自らの親族についてはしたたかに安全策を講じておきながら、従う者たちには自分も家族を犠牲にしたように振る舞う徐福。
それとも知らぬ7人は健気にも意を定め、計画を念入りに詰めていった。
非情な相談もしなければならなかった。こうなったら1人の帰還者も出してはならぬということである。
船と船乗りを帰還させたら、徐福らが帰らぬ理由が通らなくなる。海での遭難、船の破損など、帰りたくても帰れない事情が出来したと始皇帝が思い続けるようにしなければ、帰還船を使っての追っ手が出されるであろうし、よしそれがなかったとしても、徐福と主だった渡航者の家族は、たちまちにして処刑されるに違いない。
船乗りや技術者への説得は急ぐ必要はない。かの地からの出航は潮や風の条件が整うのを待たねばならず、早くても半年後だろう。その間になんとか説得しよう。万一説得が叶わなかった場合には、殺すしかない。
航海は困難を極めた。
暴風雨の中で行方の分からなくなった船2隻、明らかに沈没した船4隻。多くの船で病没者が出た。葬儀もできず、せいぜい生者が甲板に整列して死者を海中に投じるくらいであったが、それにも出ず、船倉でふて寝している者もいた。
どの船でも毎日のように喧嘩があり、それを止める者は日ごとに少なくなっていった。
それでも、なんとか済州島に着き、気力体力の回復を待って玄界灘に漕ぎ出した。航海はさらに困難を極め、またしても3隻の船が海中に消えた。九州西岸を経て現在の和歌山県新宮市に着いたころには船団は30隻をわずかに超える数に減っていた。途中で水や食料の補給のために立ち寄った港で船を捨て逃亡した者も多く、まだ航海に耐えるのにみすみす放棄された船も1隻や2隻ではない。
さて紀伊半島東岸に沿って航行していた徐福一行は、熊野川河口に椀を伏せたような形の小山を見つけ、これぞ蓬莱山と思ってここに上陸した。
東海のかなたに蓬莱山ありというのは、徐福が始皇帝を欺くためにでっち上げた話であるから、徐福自身はそこを蓬莱と思ったわけではない。数千人の同行者たちをここで永住するよう説得するための材料として利用したのであろう。
そのころは日本が縄文時代から弥生時代に移ることで、初歩的ながら農業も行われていた。そこに屯田用の五穀の種を大量に持って行った一行は当然土地の人々に歓迎された。様々な分野の知識人や技術者を連れて行ったことも歓迎された要因であろう。徐福の抜け目のない計算が功を奏したといえる。
むろん言葉の壁は大きかったが、実際に種を蒔き新しい作物を収穫する様子を見た人々が畏敬の念をもって彼らを遇したことは想像に難くない。
徐福にその気がないとはいえ、同行者たちは不老不死の薬を得るのが任務と思っているのであるから、当然それは土地の人々に伝わる。人々は一行に「天台烏薬(てんだいうやく)」という木を教える。これは不老不死とまではいかぬとしても、いくつかの薬効があると信じられていた。クスノキ科の常緑樹で、近年の研究でも根に活性酸素を消す働きがあるということが分かってきたらしい。
 |
| 天台烏薬の木に囲まれた徐福の墓・新宮市徐福公園 |
| 左端に立つのは徐福像。その右には不老の池があり、石の杭のよう |
| なものが見える。7本あり、それぞれに和・仁・慈・勇・財・調・ |
| 壮の文字が書かれている。これは徐福を支えた7人の 従者を象徴 |
| していると いう。 |
しかし、その木を持ち帰るにしても、先述のとおり当時の航海術ではおいそれと船出はできない。月が経ち年が経つうちに、秦の一行はどんどん土地の社会に同化していった。
なにしろ知識も技術も数段上であるから、誰もが大切にされ、自然のなりゆきとして土地の人との間に子が生まれるということも続く。
気候も温暖で海の幸にも恵まれたこの地は、秦の人々にとっても住み心地が良かったであろう。いつしか暴君の支配する故郷へ帰ろうという気分は薄れ、結局、徐福のもくろみは達成された。
居着いた一行の子孫はのちに「秦(はた)」という姓を名乗ったという。現代でも日本に秦姓は多くみられる。もっとも、念のため付言するが、現代の秦さんがすべて徐福一行の子孫だというわけではない。
「秦(はた)」姓は秦国の人という意味で使われた呼び名であるが、それだけなら「秦(しん)さん」と呼ばれた筈である。それが、秦の人々の中に「機織り(はたおり)」を職業とする者が多くいて、「秦の人」と「機織り職人」とが同一のイメージで捉えられたものだから、いつしか「秦(はた)さん」と呼ばれるようになった。これは中国大陸や朝鮮半島から大勢の人々が渡来してきた4世紀以降のことであり、徐福の一行とは関係ない。
ともあれ、言いようによっては稀代のペテン師といってもよい徐福は、異郷の地で望外の尊敬を集め、人々に慕われたまま、この地で70年の生涯を終えた。
今、新宮市にある徐福公園はよく手入れされ、徐福の墓には花が絶えない。
ちなみに、「徐福渡来の地」と言われ、徐福伝説が残る場所は日本各地にある。新宮市が本当に徐福終焉の地であるという証拠はなく、これからも「ご当地論争」は続くことであろう。
そしてこのことは、とりもなおさず徐福が日本の人々に広く深く敬愛されていた証でもある。
注1: 始皇帝の孤独については拙稿『秦始皇帝兵馬俑坑に思う』で触れていますので、ご笑読いただ
ければ幸いです。
注2: このときの船について、アムール川の流域で全長120メートル、幅20メートルの木造船の
遺構が発見されており、それが徐福の船団の1隻だという話がある。蓬莱に献上する男女が3千
人、スタッフを合わせればおそらく4千人にも上る大集団が皆まとまって航海できた筈はなく、
途中で沈まなかったにしても離ればなれになって漂流した船も多いであろうから、アムール川ま
で流れて行った船があったというのは不思議ではない。
また、佐賀県に残る伝承では、徐福一行は20隻で来航したとされている。途中で沈んだ船を
合わせて約30隻と考えれば1隻あたり百人余ということになる。
しかし、それより千年もあとの遣唐使船が5百人を4隻に分けて運んだということを考えると、
徐福の時代にそんなに大きな船があったとは信じがたい。
また、徐福より千四百年もあとの元寇で来襲した船は絵巻を見ても20~30人しか乗ってい
ないし、最近海底から見つかった元寇船は30メートルあるかないかという大きさである。
徐福の航海や上陸の様子を描いた絵は中国にも日本にも何点かあるが、いずれも想像の域を出
ていない。それらを見ると、漕ぎ手を含めて30人から50人ぐらいがやっと乗れる船だったよ
うに見える。
いずれにせよ、船が小さければ数が必要で、大きければ造船の技術と費用が必要である。
注3: 現在の中国では、多方面の研究により江蘇省にある徐阜村がかつて徐福村と呼ばれ、徐福にま
つわる多くの伝承が残っていることから、ここを徐福が実在した場所だとほぼ断じている。そし
てそこに現在「徐」姓を名乗る家が1軒もないこと、徐福が出航に先立って残した「徐姓を捨て
よ」という指示が伝わっていることも確認されている。
| 一度かぎりの生 | この言葉、なんとかなりませんか(7) | ||