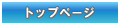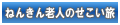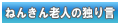九州往復ケチケチ旅行(2)
福岡といえば、忘れ難い人が・・・
台風はどうなったのか、静かな航行で熟睡しているうちに瀬戸内海を抜けた。多少の揺
れに目を覚ますとそこはもう周防灘で、6時半、新門司港に着く。
福岡については何も知らないが、まんざら縁がないわけでもない。
まず妻の郷里が福岡で、友人の結婚式に出るというので日帰りしたこともある。福岡空
港から式場に直行して、私は式の間だけ街を散策して、式後また空港に直行した。
そんなことはどうでもよいが、福岡には村野君という忘れがたい友人がいる筈だった。
学生時代、私は法学部でありながら社会思想史のゼミに所属していた。法律関係のゼミ
は秀才ばかりで私にはついていけそうになかったからで、いわば易きをねらった選択であ
る。
ところが、舐めてかかったそのゼミもどうしてなかなかのレベルで、その中に村野君は
いた。
私は専ら古代ギリシャの哲学者たち、とりわけプラトンの稀有壮大な概念に訳も分から
ず心酔していたが、村野君は北一輝を研究していた。
北一輝などという人物については教科書でしか知らぬ私であったから、無論村野君とは
意見を交わすこともなく、ただ顔を合わせれば挨拶をするという程度であった。
それが、そのうち、そうでもなくなった。
「北一輝こそ日本の救世主である。北一輝の下地がなかったら、戦後日本の民主主義は
育たなかった。軍による不当な裁判で死刑と決したときも従容として銃殺を受け入れた孤
高の生き方はソクラテスに通じる部分がある」
と、へんなところで古代ギリシャ思想に触れたりしたもので、多少は私との接点ができ、
次第に打ち解けていった。とはいえ北一輝について論ずるには私では相手にならぬと見抜
いていた彼は、私とはそんな話はまったくせず、セツルメント運動などについての話が多
かった。
当時、学生の間ではセツルメント運動に身を置くことがちょっとした流行であり、私も
いくらかは関わったりしていた。村野君も当時山谷と呼ばれていたドヤ街に出入りしてい
たようだ。
それが、話してみると、彼はその運動にかなり懐疑的であったし、ときに批判的でもあ
った。運動に加わっている者たちのヒロイズムや偽善性についても厳しく論破していたし、
なによりも参加者たちが秘かな優越感、あるいは安堵感を持っていることへの嫌悪感を語
っていた。
知力、体力、経済力、あるいは容姿でもいいが、自分よりも下にあると思える人間と行
動しているときに、優越感というほどではなくても、なんとなく安堵に似た感情を覚える
というのである。その安堵感に浸りながらセツルメント運動に参加している学生が多く、
それが鼻持ちならぬと言う。
この安堵感という観察に、私は驚きと共感を覚えた。
なるほど。恐れ入った。私のことを言われているのではないかと思うくらい図星であっ
た。
そんなこともあって、村野君の話は示唆に富んでおり、よく飲みに行った。
そのころは学生が飲むといえば焼き鳥屋かおでん屋と相場が決まっており、どちらも今
では考えられないくらい安かった。今、私は焼き鳥やおでんを食べようという気にならぬ。
あまりの高さにバカバカしくなってしまうのである。金のない学生が、金がないゆえに食
べていた焼き鳥が今1本いくらするか、おでんのこんにゃくがいくらするのか、経済のし
くみは分からぬが、貧乏学生の腹を満たしてくれた懐かしいものだけに、腹立たしさが募
る。
そんな安い店で談論風発、何時間でも過ごし、そのあとは村田君のアパートに場所を変
える。これまた学生の定番であったトリスウイスキーの丸瓶が置いてあって、パサパサの
フランスパンをかじりながら飲み直す。ときにはインスタントラーメンということもあっ
た。
そのころのインスタントラーメンには具など入っておらず、スープの粉が別袋に入って
いるなどというややこしいこともない。洗面器に麺をあけ、熱湯を入れて週刊誌で蓋をす
る。あとは3分待って食べるだけだ。インスタントラーメンの王道ともいうべきシンプル
なもので、その旨さはこの世のものとも思われぬ。
そうして飲みながら村田君から教わったことは数えきれない。私に人間観察の視点、言
い換えれば自己を客観的に見る視点を教えてくれた恩人である。
今では音信も絶え、住所さえ分からないが、風の便りでは福岡に住んでいるということ
であった。
新門司港を前にして、村田君のことが頭に浮かんだのは当然すぎるくらい、福岡という
地名が村田君の記憶にすり込まれていた。
小倉東インターから九州自動車道に乗り、八幡インターで降りて北西に向かう。途中の
コンビニで朝食を買って、車の中で食べながら宗像市のさつき松原へ。
玄界灘に面する黒松の林で、多くの松は樹齢が200年にもなるらしい。最初の植林は
黒田長政によって行われたとかいう話を聞いたことがあり、松原の長さは5kmにもなる
というから、一度は見ておきたいと思っていた。
海水浴場としても有名な所であるから、海の家などが並び、色とりどりのビーチパラソ
ルで埋まっているものと思い込んでいたら、駐車場すらない。道端に車を停めて林の中を
歩いていくと砂浜に出る。
海水浴シーズンなのに泳いでいる人はほとんどいない。海の家もなければ音楽も流れて
いない。見はるかす砂浜と松林。これ以上何を望むかと言わんばかりだ。
玄界灘沿いを南下して福岡市に入り、海の中道を通って志賀島へ。
志賀島。言わずと知れた金印の島であり、私にとっては眷恋の地である。
私が金印というものを知ったのはいつごろのことだったのか、まるで記憶にないが、お
そらく学校で習ったのだろう。中学のときに図工の授業で芋版というものを作り、それに
「漢委奴国王」と彫ったことを覚えているから、たぶんその頃知ったのだと思う。
なぜそんなことを覚えているのかというと、私は芋に文字をそのまま彫ってしまったの
で、いざ朱肉をつけて押してみると文字の左右が逆になっていて笑われたからである。と
いって、笑ったのが友達だったのか先生だったのか、その辺は漠としている。

曖昧を極める記憶の中で、ミスの記憶だけが残っているというのは、記
憶のメカニズムがどう働いているものなのか、不思議でもある。肝心の文
字にしても、本物の書体は篆書体であるが、当時の私が篆書体など書けた
筈はなく、また「倭」を「委」と書く不思議を理解していた筈もない。そ
んな私がどういう意味を持って「漢委奴国王」と書いたのか、なんにも覚
えていない。
それはともかくとして、この金印は江戸時代に甚兵衛という農民が農作
業中に偶然発見したものと伝えられている。
秦の始皇帝の兵馬俑といい、農作業中に偶然という話は夢があっていい。ただ、漢とい
う大国の皇帝が服属する小国の王に下賜した貴重な印章がなんでまた、よりもよって島の
畑に単独で埋まっていたのか。
誰かの墓に副葬されていたとか、祭祀用具などと一緒に見つかったというならともかく、
農夫の鍬にカチッと当たったというような話は、どうもでき過ぎている気がする。まさか
国王の従者が金印を持って散歩していて、何かのはずみにポケットから落ちたというわけ
でもないだろうから、そんな所にむき出しでそれだけが埋まっているというのは不自然で
あろう。
まあ、そんなことを考えるようになったのは、私が教員として生徒に金印のことを教え
るようになってからである。教えるという以上、生徒からの質問を想定して答えを用意し
ておかなければならない。
金という柔らかい素材で作られた印鑑に農夫の鍬が当たったのなら、傷がついている筈
だ、などという疑問や、漢の国王から贈られた印鑑をあちこち持ち歩いていたのか、など
という質問を考えているうちに、どうも金印発見のエピソードはかなり脚色されているの
ではないかという思いが募ってきた。
そして調べてゆくと、私の漠然とした疑問とは比べようもない論理的な疑問を呈してい
る人が沢山いることが分かってきた。よくもまあというくらい詳しく検証して、それを読
んだらもう、「あのエピソードは作り話だ」と断言できるような気がしてきた。
そこで、「分からない」と答える覚悟で授業に臨んだが、生徒からの質問はなかった。
毎年同じことを教えるのだが、発見の経緯についてはついぞ質問されたことがない。
というわけで、教えるという立場からすると金印というのは悩ましい遺物なのだが、歴
史への興味を掻き立てる素材としては一級のものであろう。
現に私は芋版事件を始めとして、金印には興味を抱き続けてきた。学研という出版社で
発行した「まんが日本史」というシリーズを全巻(17巻)購入すると実物大レプリカを
貰えるという企画があって、早速購入し、そのレプリカを授業で使ったりした。むろん我
が家の子供たちにも見せてあった。
それなのに、けしからぬことに子供たちはその金印にまるで興味を示さなかった。志賀
島には金印公園というのがあり、そこにある記念碑には「漢委奴国王」という印面のレリ
ーフが刻まれているのだが、私がその意味を説明しても「フーン」と言うだけ。娘と次男
に至っては、その記念碑に腰かけてアイスクリームを食べ出す始末だ。
海の中道を戻り、博多湾に沿って時計回りに走ると今津湾に入る。ここには後述する草
野先生に勧められた「生の松原」がある。「いきのまつばら」と読むのだそうで、私はそ
ういう所があるということすら知らなかったが、元寇の防塁が残っていると聞かされ、行
ってみることにした。
約3kmにわたる弓状の浜辺に、黒松の林が続く。比較的若い木もあるが、樹齢の見当
もつかない太い木も多い。お目当ての防塁はすぐに見つかった。砂に埋もれて高さは感じ
られないが、築造当時は1.8mくらいあったらしい。軽装での集団戦法をとっていた元
軍のことであるから、これを乗り越えることはさほど難しくはなかったと思われる。
元寇については少々勉強していたので私の感慨は浅からぬものがあったが、その戦闘に
ついてここで受け売りを書き連ねては顰蹙を免れないので自重する。
ただ一つ、返すがえすも悔しいことがある。有名な蒙古襲来絵詞の中の、竹崎季長が馬
に乗って蒙古軍と奮闘している絵は、まさにこの生の松原での情景だということを、旅行
を終えてから知ったことである。
教科書にも載っているその絵を生徒に見せながら、私は熱く元寇について語ってきた。
軽装で集団戦法をとる蒙古軍が機動的であるのに対し、重い鎧を着た武者が一騎駆けで
敵に向かう日本軍はいかにも時代遅れに見える。おまけに乗った馬が敵の矢に当たって血
を流し、後ろ脚を跳ね上げて暴れるものだから、竹崎季長は落ちないようにしがみついて
いるだけで精いっぱい。蒙古軍から見たら滑稽ですらあったに違いない。
そんなことを教壇から得意になって解説していた私は、あるときふと、場面に描かれた
矢がほとんど蒙古軍に向かって飛んでいることに気づいた。(今この文を書くにあたって
改めてその絵を見ると、蒙古軍の方に向かって飛んでいる矢は17本、日本軍の方に飛ん
でいる矢は4本しかない)
一騎掛けとは言いながら、実際には鎧武者の後方から激しく援護射撃を行っていたとい
うことになる。はてさて、鎌倉時代の戦法とはいかなるものだったのか。
生徒を前にした、いわば本番中にそんな疑問がよぎった私は説明に詰まり、汗顔三斗の
思いで教室をあとにした。
そんな苦い思い出もある絵詞の舞台に今まさに自分が立っているということも知らずに、
ただ防塁としてのみ見てきた自分の無知に歯ぎしりするほどの悔しさを覚える。
しかしこの時はそうとは知らず大満足で、元寇についてひとくさり子供たちに語ったあ
と、次の目的地、大宰府天満宮に向かう。
大宰府といえば菅原道真ということになるが、ここで道真について講釈を並べたのでは
鼻白む人が多かろうと思うから、話の方向を変える。
大宰府というと、思い出さずにいられない人がいる。
その人は小学校の同級生で、サカガミクニコさんといった。
むろん本名ではない。ご本人のプライバシーに関わるとか個人情報保護法に触れるとか
いう理由ではない。その人は私にとって眩しいくらいに輝いている人で、こんな駄文の中
に本名を載せるなどということは恐れ多くてできないのである。
少し思い出を語ることをお許しいただきたい。
その人はクニコという名前から、女の子たちの間では「クンチャン」と呼ばれていた。
勉強はできるし美人だし、なによりお嬢様で、私たち洟垂れ小僧どもでは当然相手になら
ない。といって、お高くとまっている訳ではなく、休み時間の“ゴム跳び”などではよく
「一緒にやろうよ」と声を掛けてくれたりした。
その気になって参加したりすれば男子仲間から手ひどいいじめを受けることは必至であ
るから、私も素知らぬ振りをしていたが、もし一緒に遊べたら、小学生にして早くも「思
い残すことがない」くらい舞い上がったであろう。
あるとき、男子の中で「誰かクンチャンと呼んでみないか」という話が出た。そんなこ
とができる訳はない。
そのうち誰言うともなく、私にそれをやらせようという風向きになってきた。いつもの
ことで、何か厭なことや面倒なことがあると必ず私に回ってくる。話の展開はよく覚えて
いないが、最後に、渋る私は腰抜けだというような話になってきたと思う。
そうなっては引けない。
その日だったか次の日だったか、その人が学校の前の文房具屋さんにいると聞いた私た
ちは店の前で待ち構えた。
出てきた!
数人のガキどもが遠巻きにする中、私は大声で、「クンチャン!」と叫んで、一目散に
逃げた。
翌日、このことはクラス中に知れ渡っており、その結果、あろうことか私はすべての男
子から村八分になった。
思えば、周囲からそそのかされ、けしかけられ、あるいは懇願されて何かやると、たち
まち責任を一身に押し付けられ、あまつさえその周囲が敵に変わる、というのはその後の
人生でいやになるほど経験している。この事件はその第1号だったかも知れない。
長じて、その人はちょっとやそっとでは入れない難しい大学に入った。英語部だかなん
だかに所属していたようで、学園祭だかなんだかで、その部が菊池寛の『父帰る』を英語
でやるというので、私も観に行った。「なんだか、なんだか」とはっきりしないが、舞台
の流れは鮮明に覚えている。
いたく感動した私はそれが忘れられず、のちに勤務先の文化祭で教員有志を募り、英語
劇をやった。めくら蛇に怖じずとはこのことで、並居る英語教員を差し置いて台本を書き、
演出家をきどって指図もした。南極点一番乗りを目指してアムンゼンに負け、帰途全員が
凍死したイギリスの探検隊の悲劇を扱ったもので、隊長ロバート・ファルコン・スコット
の役は、誰あろう、この私であった。
なんのことはない、私が私のために仕組んだ自己満足の極みというべき企画であったが、
若気の至りとは恐ろしいもので、翌年もまた日本の神話を題材に同じことをやった。
今にして思えば汗顔三斗であるが、そのエネルギーがあの『父帰る』からきていたこと
は間違いない。
後年、その“クンチャン”は結婚した。女神様が結婚するなどということは想像したこ
ともないので私を含むかつてのガキどもは仰天し、その幸運な“ご亭主殿”を妬んだ。
しかし切歯扼腕したところで、所詮私ら洟垂れとは無縁の世界の人であるから仕方がな
い。
その人、すなわち“クンチャン”がご主人の転勤で福岡市に住んでいたとき、たまたま
私が福岡に出張することになった。出張先の宿から電話をすると幸い在宅で、折角ここま
で来たのだから家に寄らないかと言う。
私はうろたえて、そんなつもりで電話をしたんじゃない、面識もないご主人に迷惑はか
けられないと固辞したが、「素通りするとは水臭い」とまで言われ、ついついその気にな
って言葉に甘えた。
ご主人は実にできた方で、夕食時に突然電話した馬の骨を宿まで迎えに来てくれ、かつ
送ってくれたばかりか、人をそらさぬ話術で長時間付き合ってくれた。
そんな忘我の時間の中で、私が明日は仕事がないので大宰府天満宮に行ってみようと思
うと話したところ、“クンチャン”が、それならお土産に梅が枝餅を買って帰るといい、
大宰府ならではの餅菓子で味は保証する、と熱心に勧めてくれた。どの店で買っても後悔
はさせないが、その中でも一等の店がある、と言って、ある店の名前と位置をしっかり教
えてくれた。
その店は店内でお茶と餅を味わうことができ、なるほどその旨さはすこぶるつきであっ
たから、私は向こう三軒両隣の分まで土産に買い込んだ。
ところがこの梅が枝餅というのは意外に重く、布製の旅行バッグが膨らむほど詰め込ん
だのは愚かの限りで、帰りに羽田で飛行機を降りようとしたとき、狭い通路でバッグの柄
がぷっつりと切れてしまった。うろたえながらバッグを両手で抱きかかえて機内を歩いた
姿は、今思い出しても見っともないものであった。
話を家族旅行に戻そう。
 |
| 天満宮の大楠 |
その大宰府天満宮を、お参りというよりは観光気分で見て歩い
たあと、そこからほんの数分の距離にある草野先生のお宅を訪ね
た。
草野先生というのは私の勤務先の先輩で、私が最も敬愛する人
物である。
野球部の監督をしていたが、校内の野球部寮にご家族と一緒に
泊まり込み、早朝から深夜まで生徒の面倒を見ていた。
勝つことだけを求められる高校野球の世界では、勝つためなら
何をしてもいいという風潮がある。部員たちは勝利に役立たぬ娯
楽などをことごとく禁じられるばかりか、クラスの役員や掃除当
番も免除されるなど、おそよ教育の場にふさわしくない扱いを受
けていることが多い。
草野先生はそうした風潮について口にすることはなかったが、
ご自分は部員たちに他の生徒とまったく同じ責任を果たさせていた。厳しい練習の合間に
娯楽の機会も与えていた。
あるとき、私は先生から、部員たちの息抜きに釣りをさせてやりたいという相談を受け
た。
学校からバスで小一時間ほどの所におあつらえ向きの渓流があるにはある。しかし、野
球一筋の生徒ばかりで、釣竿など持っている者はいない。私は釣りを趣味としていたが、
5,60人もの生徒に貸せるほどの竿を持っているわけもない。
先生は「竿はこちらで用意します」と言って、部員たちと学校の裏山に入り、物干し竿
として使えるような太い竹を100本近く切ってきた。いやしくも渓流釣りであり、相手
はウグイやオイカワという小さな魚ばかりである。物干し竿で釣ったって、手応えもへち
まもありはしない。
バスを降りた数十人の生徒たちが草野先生を先頭に、手に手にその竿を持って歩く様は、
さながら木下藤吉郎率いる足軽軍団が槍ぶすまを築いて行進しているようで、壮観といえ
ば壮観、滑稽といえば滑稽であった。
さらに渓流に着き、岸辺に並んだ生徒たちが対岸に届きそうな長くて太い竿を並べてい
る光景も、敵を前にした足軽の先鋒隊を彷彿とさせ、どう見ても渓流釣りという風情では
ない。
むろん釣れる筈もなく、ほとんどの生徒は1匹の魚も手にすることなく一日を終えたの
だが、皆不思議と楽しそうで、平素鬼も天狗もかくやという形相で部員たちを叱りつけて
いる草野先生も慈愛に満ちた笑顔で冗談を飛ばしていた。きつい九州弁で、生徒たちがど
れだけ理解していたのかは不明だが、私まで幸せになるような一日であった。
そんな好人物であるから、人望もあつく、野球の県大会ともなると我々は勝手連ともい
うべき応援団を組み、球場に押しかけた。とかく高校野球となると勝利至上主義がまかり
通り、監督は勝つためなら部員を修学旅行に行かせずに練習させるなどということを当た
り前のようにしていたから、他の教員からは浮き上がった状態になりがちであった。学校
行事として生徒を応援に動員する際にも、私などは心から応援するという気にならず、勝
つと、やれやれこれでまた野球部様の専横が増幅されるのかと憂鬱になったりしたもので
ある。
しかし、草野先生が監督をされている間は、夢中になって応援した。勝つとその晩は皆
で居酒屋に繰り出し、次の相手は○○高校だ、なにするものぞ、などと、自分が試合をし
ているわけでもないのに、選手起用から作戦までカンカンガクガクの御託を並べて飲み続
けた。むろん負けたら負けたで、草野先生を男にしよう、などと気炎をあげ、要するに草
野先生をダシに飲んでいたわけであるが、他の監督でそういうことをした記憶は一度もな
い。
その草野先生はご両親が高齢でもあり、長男としての事情もあったようで、退職して郷
里の高校に勤め、やはり野球部の監督をしておられた。
その後は年賀状を差し上げるくらいのお付き合いしかなかったが、尊崇の気持ちはずっ
と抱いており、この旅行で福岡に行くのを機に、是非お会いしたいと思って手紙を出した
ところ、快く予定を開けて待っていてくださったのである。
久しぶりに聞く先生の九州弁は心地良かった。お人柄も在勤当時そのままで、話される
内容も奥が深く、九州弁には慣れていない我が家の子供たちも頷きながら聞いていた。
かくかくしかじかで、福岡というとあの人この人のことが思い出され、つい話がそれて
しまったが、それもまた旅の醍醐味であり、福岡という土地を身近に感じる所以でもある。
| 九州往復ケチケチ旅行(1) | 九州往復ケチケチ旅行(3) | ||