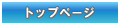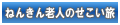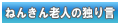中国西域見聞記(2)
西遊記の舞台を訪ねて
トルファン盆地は世界で2番目の低地で、もっとも深い所は海抜がマイナス155メー
トルもあるという。当然暑い。
一日の平均気温(最高気温ではない)が35度を超える日が年間100日以上あるとい
うから、それだけでもう住む気は失せるが、過去の最高気温は49.6度、そのときの地
表温度は83.3度というからすさまじい。
年間降水量が16ミリ、年間蒸発量が3千ミリという数字も現実離れしていて見当がつ
かない。
そんな土地に草木が生える筈はなく、そのとおり見渡す限り沙漠なのだが、そんな沙漠
の中にトルファンの町が見えてきた。そこだけ木々が茂っており、なるほどオアシスとい
うのはこういうものかと思う。
町に入る手前でカレーズを見るために農家に寄る。
先述のとおり、そのままでは農業はおろか、人間が住むこともできないこの土地で、人
々は地下に天山山脈の地下水を通すための水路を巡らした。総延長5千キロにも及ぶとい
うその水路のおかげでトルファン盆地は地中の乾燥を免れ、オアシスでのブドウ栽培、瓜
栽培を続けている。まことに壮大な話である。
しかし、ガイドの金さんによれば、沙漠というのはどこでも地下水が豊富なのだそうで、
それを水路にまとめているだけのカレーズを外国人が大騒ぎするのが理解できないらしい。
それでも外国人観光客が喜ぶとなれば案内はするし、見学した農家もちゃんと別棟を土産
物屋にしていた。
確かに話で聞くカレーズは壮大だが、見るとなると、わずかに開いた水汲み場で穴の中
を覗くだけで、それも数メートル先までしか見えないから、とくに面白いものでもない。
ようやくトルファンの町に着いた。
とりあえず緑州賓館というホテルに入る。火州と呼ばれる砂漠地帯にあるオアシスであ
るから緑州というのは気の利いた命名だ。
ロビーはかなり混雑している。入口にウィグル族らしい女性がなにやらたすきをかけて
笑顔で客を迎えているが、愛想のいいのはそこまで。
日本語の達者な女性が売店で客に商品を勧めているが、これはもう、なにがなんでも売
りつけようという魂胆だけが表に出ていて感じが悪い。
まず昼食になるが、料理そのものが粗末なのはまあいいとして、ビールがまったく冷え
ていなくて、味も悪い。
部屋に入り、小用を足そうとして便座の蓋を上げたところ、それがバタンと落ちてしま
う。何度やっても同じ。あとで伊藤さんは一計を案じ、バスマットをタンクに載せて、そ
れで便座の蓋を押さえる方法を考案した。
さて売店に行き、持崎さんがTシャツを買った。
日本語を話す店員はおらず、ガラスケースの内側で漢族らしい女店員が2人、何か無言
で食べていたが、持崎さんの質問に対して面倒臭そうに Twenty と答える。 中国人店員
の横柄な態度に一々腹を立てていたら旅行はできないので、持崎さんは1枚を買った。と
ころが渡されたつり銭が足りない。もう一度値段を訊くと、ぶっきらぼうに Twenty-five
と言う。
そこからは全然譲る風がなく、言い間違えたとも言わない。
私は切手を買おうと思って POST OFFICE と書かれた所に行ったが、人がいない。フ
ロントに行って切手が欲しいと言うと、Nobody! Tomorrow. とぶっきら棒に言ってど
こかに行ってしまった。
まったく、どいつもこいつも。そんなに接客がいやならラクダのクソでも掃除してれば
いいではないか。
ま、いいか、目的は火焔山だ、ホテルじゃない。そうでも思うしかなかった。
午後5時過ぎ、といっても北京時間だし、その北京も日本との時差はない。経度からす
ると日本より3時間以上太陽の動きが遅れているわけだから、日本の感覚でいうと2時過
ぎということになる。
その5時過ぎに、マイクロバスで火焔山に向かう。
町を出ると、ただただ平坦な礫沙漠の中に1本だけ、東に向かってどこまでも続く道が
ある。車窓左手に赤茶けた裸の山並みが続くほかには何もない。
と、その道を歩いている男がいる。紺の国民服を着て、大きな荷物を肩から下げ、いか
にも暑そうに歩いている。
それは暑いだろう。なにしろここは地表の岩に卵を落とせば目玉焼きができると言われ
ているトルファン盆地だ。いったいどこまで行くのか。この先、歩いて行ける距離に村や
町などありそうには思えぬ。
すれ違う車もほとんどなく、単調な景色の中をガタガタと走って行くと、左前方に火焔
山が見えてきた。西遊記に出てくる火の山であり、「空に飛鳥なく、地に走獣なし」と形
容された灼熱地獄である。

遠目には、ただ草木が生えていないというだ
けで、灼熱地獄というほどの山には見えなかっ
たが、だんだん近づくにつれ、生というものと
は無縁のすさまじい山容を顕わしてくる。確か
に写真で見た火焔山だ。
さらに走るとバスはやがてその山中に分け入
り、両側に急勾配の山肌を見上げながら走るこ
とになった。いよいよあの西遊記の世界に入り
込んだのだと思うと、自分でも分かるほど興奮
し、それに反比例するように無口になってしま
うのが分かる。
しばらくして、急にバスが止まった。西遊記の登場者の像を配した土産物屋のような所
だ。垢抜けない、ごてごてとした飾りに包まれたその店の佇まいが、折角の荒涼とした景
観をぶち壊している。むろん入る気にはならず、人気のない山の方に歩いて行った。
そこは確かに火焔山の真っ只中に入り込んだという感じで、圧倒される。
岩肌が風化によって砂となり、山の襞に溜まって赤い急斜面を作っている。砂、それも
誰にも触れられたことのない砂を採りたくて、その砂を登った。足がふくらはぎまでずぶ
ずぶと潜る。身体を支えようと手をつくと、それも潜る。
1メートル登っても砂と一緒に1メートル滑り落ちるので、ちっとも進まない。
よろけた弾みに腕時計が落ちた。ワンタッチ式のベルトだったので、ちょっとした加減
で外れたらしい。
スポッと砂に埋まった時計を掘り出そうと砂を掻いたが、見つからない。焦って砂を掻
き回す。肘まで砂に突っ込んで必死で探るが、見つからない。そうしている間も砂は絶え
ず流れ落ちてゆく。おそらく、砂と一緒にずっと下まで滑り落ちてしまったのであろう。
結局時計は諦めたが、あの砂では永遠に埋もれたまま出てこないかも知れない。
気を取り直して再び火焔山を仰ぎ見る。全山燃え盛るこの山に行く手を遮られた三蔵法
師一行。孫悟空が芭蕉扇で火を消す場面が有名である。山に木がないのだから山火事とい
う概念はない筈なのに、それでも火焔山と名付けられたのは、地獄の如き地表温度による
陽炎のため赤茶けた山全体がゆらゆらとまるで炎のように見えるからだという。
確かに暑い。しかし未体験の暑さを期待していた私にしてみると、それは取り立てて騒
ぐほどのものではなかった。このくらいの暑さなら沖縄でも経験している。
拍子抜けした気分で再びバスに乗り、すぐ近くのベゼクリク千仏洞へ。崖にいくつもの
横穴が掘ってあり、その中に仏画が描かれている。壁は日干しレンガを積み重ねた上に壁
土を塗ってあるのだが、それがあらかた剥がれ落ちているため、壁画はほとんど残ってい
ない。
たいして面白くもないので、下の河原に下りる。一木一草とてない火焔山の中で、ここ
だけは水が流れ、木も草も豊かに生えている。あとであの川は何という川なのかとガイド
に訊いたところ、名前はついておらず、地元の人は小川と呼んでいる由。
帰り道。来たときと同じ道を今度は西に走る。当たり前だが同じ景色だ。右側の山並み
を除いては地平線まで何もない。いくら異郷の景色とはいえ、こう何もないといささか飽
きてくる。
そのとき、まっすぐ延びた道の先に人が見えた。徐々に近づいてきたその人は、来ると
きに見た、大きな荷物を肩に下げたあの男性だ。年は30代後半か40代前半だろうか。
さっき見てからはすっかり忘れていたが、あれから私たちはかなり走り、見物や休憩を
挟んで時間もかなり経っている。それなのにこの男性は、この暑さの中をさっきと同じ方
向に向かってまだ歩いている。この先には景観を損なう土産物屋と、千仏洞近くの小さな
集落を除いては建物など何もなかった。
いったいどこまで、何のために歩いているのだろう。
私が何をしたわけでもないのに、一応冷房の効いたバスに乗って移動している自分がな
んだか後ろめたいような気分になってしまった。
あのときのあの男性の服装や髪形は今でも目に浮かぶ。
まだまだ陽が沈む気配はなく、アスターナ古墳群と高昌故城を回る。
アスターナ古墳群とは6~7世紀の地下墓で、南北2キロ、東西5キロの範囲に約千基
が残っているらしい。といっても我々が案内されたのはそのうちの3基で、それ以外には
墓らしいものは見えなかった。
もっとも古墳といっても墳丘はなく、平地に斜坑があって突き当りに墓室があるだけだ
から見えなくて当然ではあるが、それにしても入口ぐらいは見えていいだろうし、それぞ
れの墓の上に印ぐらいはつけておいてもいいと思う。
それが何もない。ただの沙漠である。公開されている3基以外は埋め戻されているのだ
ろうか。とにかく荒涼とした無機質な空間が広がるだけで、墓地というにはあまりにも殺
風景だ。
最近ある本でここアスターナ古墳群を紹介する記事を見たところ、延々と塀に囲まれ、
料金所らしいものまであった。そこを入ると中にはいくつかの建物と、奇怪なモニュメン
トや、人よりずっと大きい十二支像が建っていた。刈り込まれた植え込みの中には緑の草
地が広がり、それを縫う遊歩道は舗装され、さながら広大な公園のようであった。
いいのか悪いのかは判らないが、私はもうそこに行ってみたいとは思わない。
私たちが行ったときは上記のような沙漠だけであるから、被葬者が乾燥によってミイラ
になったという話にも説得力があった。確かにそこで見たミイラはエジプトのような人工
的なものではなく、自然乾燥によるミイラであることが一目で判るものであった。
現在のあまりにも整備された公園風の景色からは千数百年前の埋葬文化は想像しようが
ない。
高昌故城では入口からロバ・タクシーに乗る。ロバに荷車を曳かせて客はその荷台に乗
るというもので、1人2元。
小さな子供が一緒に乗り、やけに愛想がいいので写真を撮ると、すかさずチップを要求
される。余った人民幣で2角渡したが、こんな子供が当たり前な態度で金をせびるとは。
高昌故城は5世紀から6世紀にかけて栄えた高昌国の城塞跡で、東西1.6km、南北
1.5kmの広さがある。
とはいえ、建物はすべて日干しレンガを積み重ねたもので、今はことごとく崩れており、
往時の面影を偲ぶのは難しい
ハリネズミらしい動物の死骸があり、それにスカラベが2匹ついている。スカラベとい
うのは古代エジプトで太陽神ケプリと同一視され崇拝された甲虫で、ファーブルの昆虫記
にも出てくる。見るのは初めてで、遺跡よりも記憶に残っている。
入口に戻ると、売店で西瓜が出る。中国では土産物屋で必ずといっていいくらい西瓜が
出る。喉を潤すにはかっこうで、ありがたい。
何も買わずに西瓜だけ食べるのは気がひけるが、どっこい敵さんは黙って食べさせてく
れるわけではない。次々と土産物を指して、あれはどうかこれはどうかと、おちおち食べ
てもいられない。
このときもあれこれ掛け軸を勧められた。1本2万円だが、日本円で払うなら1万5千
円でいいと言う。こんな所でも日本円を欲しがるのかと思ったが、安くなるからといって、
要らないものは要らない。
断ると、あっさり1万円に下げてきた。本当の値段はいくらなんだ。
結局西瓜のただ食いだけで終わった。ちょっぴり気が咎めるが、西瓜一切れで不要な物
を買わされてはかなわないから、割り切ることにする。
ホテルに戻って夕食。昼食のときに冷えていないビールで閉口したので、全線随行の王
さんに頼んで冷たいビールを買ってきてもらう。ホテルには無くて、ほかを探したらしい。
1本2.5元だった。
4日目、朝食の席でまたもや行程変更の知らせ。今夜汽車で柳園に行くという予定は取
りやめて、明日、飛行機で直接敦煌に行くという。その飛行機は、トルファンに民間の空
港がないので、軍の飛行場を使ってチャーター便を飛ばすのだそうだが、それもまだ切符
は確保できていないとか。
この日は交河故城とかイスラム寺院とか見て回ったが、とりたてて強烈な印象はない。
トルファン葡萄溝という所は観光ぶどう園といった所で、人が多い。小さな種無しぶど
うとハミウリを食べた。どちらも美味かった。
ただ、便所が汚いのには参る。建物の外にまで匂いが漂い、中は汚物が溢れたのではな
いかと思われる状態で、目が痛くなるほどの臭気が充満している。
結局そこで用を足す気にはなれず、ホテルまで我慢する。
ところがホテルに着くと、エレベーターのドアが開かない。何度もボタンを押している
と、近くに腰かけていた若い女性従業員が「没有(メイヨウ)」と言う。エレベーターガ
ールがいないという意味らしい。そんなものいなくたって自分で操作すればいいのだが、
ドアが開かないのではいかんともしがたい。
従業員はそれ以上こっちを見ようともしないので、結局階段をつかって部屋に戻る。
夕食のあと、トルファンの民族舞踊というのを観に行く。時間は10時だが、空を見る
とまだほんの宵の口のように明るい。結構な距離を歩く。道はずっとぶどう棚の下を通っ
ている。
着いた所はほかのホテルの庭らしい。トルファンの風景を描いた背景がセットしてあり、
椅子が数十脚並べてある。一番前の席について始まりを待つ。
すぐ前にいかにもやる気のなさそうなバンドの連中が所在なさげに坐っている。
そのうち、民族衣装の女性が挨拶を始めた。ウィグル語、英語、そして日本語。やはり
ここでも日本人客が多いとみえる。
踊りはこの辺の民族舞踊なのだろう、リズミカルで美しい。ウィグル族、カザフ族、ウ
ズベク族などの歌と踊りが次々と披露されるが、これがみんな「美しいトルファン」とか
「すばらしいトルファン」とか、いわゆるご当地ものばかり。
それでも衣装も動きも素晴らしく、踊り子たちも愛くるしいので私は大いに乗ってきた。
驚いたことに、さっきまでやる気のなさそうに見えたバンドの連中が、見違えるように
張り切って演奏している。
最後に観客を踊りに誘い出し、何人かの日本人が声をかけられるが皆尻込みして出て行
かない。そのままでは空気が白けると思っていたら、私に誘いがきた。ホイキタとばかり
に立ちあがったのは言うまでもない。
派手に踊りまくりながら、私は思っていた。
「やっぱり、ここは中国ではない」
| 中国西域見聞記(1) | 中国西域見聞記(3) | ||