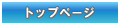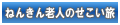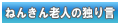ヨーロッパ美術巡り(4)




平素の不勉強を恥じもせず
8日目はバスで近郊観光に出る。
ビーチ沿いの道は「英国道路」と名付けられた観光道路で、貨物車は通行禁止だそうだ。
アンティーブのヨットハーバーでバスを降りる。いかにも金持ちの趣味といった豪華な
ヨットが無数に停泊しており、ツアーの客の中にはそのヨットをバックに写真を撮ったり
している者もいるが、何の意味があるのだろう。
そこからほど近い所に市庁舎があり、広場でガラクタや食料品の市をやっている。大変
な賑わいで、案の定、メンバーの一人がジプシーの子供たちに財布をすられそうになる。
少し歩いてピカソ美術館へ。グリマルディー家が持っていた城の一角をピカソがアトリ
エにしていたそうで、その城をそのまま美術館にしたという説明だった。当然ピカソの作
品が中心だが、その他の作家のものもある。
ピカソの絵はいくら説明を聞いても解らない。キュビズムとか言われても、なぜ前から
見た顔と横から見た顔をまぜこぜに描くのか、そう描くことによって一点から見て描いた
ものより良いことがあるのか、などなど、とにかくとんと解らない。
さらにやっぱりと言うか、ピカソも写実的な絵がちゃんと描ける。ここにはそうした絵
も展示されており、「なんだ、ちゃんと描けるんじゃねえか」と思ってしまう。
どうも絵は解らないので、どうでもいいことを書こう。何かの本で知って、面白いので
書き写しておいたことがある。それはピカソの名前だ。彼は通常パブロ・ピカソと呼ばれ
ているが、その本名は
パブロ・ディエーゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ホアン・ネピムセノ・マリア・
デ・ロス・レメディオス・クリスピン・クリスピアーノ・デ・ラ・サンテシマ・トリニダ
ード・ルイス・イ・ピカソ
というのだそうだ。日本の寿限無には敵わないが、相当な名前と言えるだろう。
こんなことを書くというのが絵画音痴ぶりを示すことになるのは承知しているが、どう
見栄を張ってもピカソの絵を解説することはできないので、仕方がない。
この美術館は城だったというだけあって、広いバルコニーがある。眼下は紺碧の海で、
映画『エーゲ海に捧ぐ』の一シーンそっくりに、人の泳いでいるのが見える。
と、伊藤さんが
「ジャコメッティだ!」と叫んだ。どうもよく叫ぶ人だ。
ジャコメッティなんて聞いたこともない私は例によってその言葉が聞き取れず、数回聞
き直してやっとそれが彫刻家の名前だと知った。
見るとバルコニーのそこここに、奇怪な彫刻が並んでいる。針金に紙粘土を貼りつけて
原型を作ったような人物像だ。高さは大きいものでも1メートルくらいだろうか。ロダン
のように写実的な彫刻なら見ていて飽きないが、こういう像はどうも私には合わない。
それなのに今私が美術館などで「これはジャコメッティじゃない?」などという台詞を
吐くのは、ひとえにこのときの伊藤さんの叫びが耳に残っているからである。
ヨットハーバーまで戻る途中、ジプシーの子供たちがバックパックの若者から財布をす
るのを見た。
通りかかった大人が子供を取り押さえ、財布を若者に返してやった。子供は叱られただ
けで悪びれる様子もなく逃げ去ったが、ともあれ財布は若者に返った。
とはいえ、ガイドの話ではその大人もグルで、財布の現金は抜き取ってあるという。そ
うとも知らず礼を言っている若者が気の毒だ。
カンヌを抜け、エステレルの山岳地帯に入る。この辺りはミモザの密生地だそうだが、
数年前に大規模な山火事があったとかで、真っ黒に焼けた木々が延々と続いている。
ミモザ、ミモザ。日本人ガイドのYさんはミモザに何か思い入れでもあるのか、何度も
何度もその名を口にし、今でも私はミモザを見るとYさんを思い出す。
Yさんについて、私は何も知らない。なぜフランスにいるのか、独身なのか亭主持ちな
のか、子供はいるのかいないのか。ガイドをやりたくてフランスに来たのか、それとも別
の志が破れて生活のためにガイドをしているのか。
海外ツアーで出会う現地の日本人ガイドというと、言葉が達者で知識が豊富、顔が広く
て行動力があるというイメージが強い。とくに女の人はときにこれ見よがしの服装でさっ
そうとしていることが多い。
それがこのYさんの場合、アイロンの効いていない無地の白シャツに、これまた質素を
絵に描いたようなスカートで、化粧っ気もなく、装身具の類もまったくつけていない。声
にも覇気がなく、一生懸命の喋りがなにか痛々しい。
私と伊藤さんはホテルで飲みながら、勝手な推測を並べていた。親の反対を押し切って
きざなフランス野郎と結婚してここまで来たが、その男に捨てられ、おめおめと実家にも
帰れず、安アパートに住んで日本人ツアーのガイドで糊口を凌いでいる、というのがそれ
だ。
今でもふと、あのYさんはどうしているだろうと思うことがある。
「ビクトワール山だ」
また伊藤さんが叫んだ。
バスがプロバンス地方に入ってしばらくしてのこと。これまた私には何のことか分から
ず、え? と訊き返す。
セザンヌの絵に描かれた山がサント・ビクトワール山というのだそうで、今前方に見え
てきた山がそれだというのである。バスに揺られながらぼんやりと眺めている景色の中か
ら絵画の中の山を見つけ出すというのは大変なことで、よほどその絵を見慣れた人でなけ
ればできることではあるまい。
「ふーん」
これまた私のいつもの返事で、なんとも情けない。
とりあえず写真に撮り、帰ってから調べてみると、なるほどその山だ。セザンヌという
のはテーブルの上に置いたリンゴや梨ばかり描いていたように思い込んでいたが、実際に
は人物も風景もいろいろ描いており、わけてもビクトワール山は何枚も描いているらしい。
また少し、勉強になった。
そのセザンヌの家を見るということで、エクサン・プロバンスという町に入る。プラタ
ナスの並木が見事だ。
高台の斜面に建つ石造りの家で、アトリエは2階にある。天井が高くて窓の大きな部屋
で、イーゼルやパレットなどがいかにもそれらしく残されているが、とくになんというこ
ともない。セザンヌがよく描いた骸骨やリンゴが置いてあるが、骸骨はともかく、リンゴ
はなんだかわざとらしい。
セザンヌは描く対象を徹底的に観察し、リンゴなどは筆をとる前に腐ってしまったとい
うことだが、ここに置いてあるリンゴもまさしく腐っており、わざわざそんなものを置い
てあるところに演出を感じる。
私にはアトリエよりも庭の方が良かった。ちょっとした森の趣で、小径が縦横に走って
いる。緑陰にはテーブルもあり、お茶でも飲みたい気分だ。
アルルの町に着く。城壁に囲まれた小さな町で、闘牛場もある。ガリアの県庁が置かれ
ていた所だそうで、石畳の道にも歴史が感じられる。
シーザーがポンペイウスと対立したとき、アルルはシーザー側についた。シーザーが勝
ったことで、アルルの地位が格段に上がった。
そんな歴史を踏まえてか、私たちの泊まったホテルは「ホテル・ジュリアス・シーザー」
という名であった。荷物を置いて、すぐに散歩に出る。
市庁舎前の広場にはなぜかオベリスクが立ち、その前で中国の天安門事件の写真が展示
されている。漢字で「六月四日、北京的虐殺」と書かれている。
翌日は午前中が市内観光であった。
観光といっても、一応美術巡りのツアーであるから、ゴッホの足跡を訪ねるという趣向
になっている。
ゴッホは30代の半ばに、1年あまりこのアルルに住んでいたそうで、代表作の多くが
ここで描かれている。
その1枚が『アルルの跳ね橋』で、ツアーは当然この橋に行く。ラングロア橋というの
がその名で、レンガ積みの橋の中央部が跳ね橋になっている。この絵は高校のときの教科
書にも載っていたもので、細部はともかく、大まかな形は頭にあった。
だが、どうも違う。どこがどうと言えないものの、私が思っていたゴッホの絵とは違う
のだ。写真に撮って、家に帰ってから画集と比べてみると、やはり違う。

ゴッホの絵では、両岸
から張り出したレンガ橋
が中央で切れていて、そ
こに木製の跳ね橋がつい
ている。
写真のものは狭い水路
の両岸がコンクリートの
平場になっていて、そこ
から直接跳ね橋が掛かっ
ている。
絵では草地になってい
る土手も、今はオリーブ
のような低木で覆われて
いる。
まあ、ゴッホが描いた
のはちょうど百年前であ
るから、木造の橋は当然
架け替えられているし、
レンガ橋の部分が撤去さ
れ、そこにコンクリートの土止めを兼ねた平地ができていたとしても文句を言う筋合いは
ない。
と、無理に自分を納得させようと思っていたら、別の本にがっかりすることが書いてあ
った。ゴッホの描いた橋は第二次大戦で破壊されてしまい、別の場所に復元されたという
のである。つまり、今観光客が見るものは、場所も橋も別物なのだ。
しかし、それならわざわざ見に行くこともないのではないか。
そうとは知らず、なんとなく絵のイメージとのずれを感じながらも、ゴッホが写生をし
た場所を見たつもりになって、次の見学場所であるアルルの療養所に移動。ゴッホはここ
で療養生活を送ったそうで、『アルルの療養所の庭』という作品を残している。
その絵を見ていないばかりか、そういう絵があることすら知らなかった私はとくに感慨
もなく、肝心の庭を見てもただきれいだなと思っただけで、ゴッホゆかりの場にいるとい
う高揚感もなかった。
昼過ぎ、バスでアルルを出発。
プロヴァンス地方ではミストラルという強風が吹き、冬は猛烈に寒いという。その風を利
用するのだろう、あちこちに風車があり、アルフォンヌ・ドーデの『風車小屋便り』もこ
こで書かれた。
と書くと、いかにも私がその『風車小屋便り』を愛読しているようだが、実は一度も読
んだことがない。なんでもフランスの小説家ドーデがプロヴァンスに住んでいたとき、こ
こからパリの読者に宛てて手紙を書くという構成で短編集を出したらしい。これもあとで
知ったことだ。
そのドーデの祭りというのが開かれていた。丘の上の風車の下に民族衣装を着た男女が
大勢集まっているので見に行く。馬に乗った男たちが格好良かったが、どうも次々とお偉
いさんが挨拶に立ち、いつまでも続いているので飽きてしまった。どこの国でも空気が読
めずに長い挨拶をする御仁は多いとみえる。可愛い衣装の女の子があくびをしている。
アビニョンに着く。
歴史的に重要な場所らしいが、どう重要なのかは分からない。フランス王フィリップ4
世がカトリック教会の権威を利用するために教皇をローマからアビニョンに移したという
ような説明があったが、それが歴史を動かすような出来事だったのか、どうもよく分から
ない。
ともあれ栄えた時代があったようで、城壁に囲まれた歴史地区では繁栄の名残りが随所
に見られる。その教皇庁の前で、ペルーあたりから来たのだろうか、5~6人の若者がア
ンデスの音楽を演奏している。ギターケースに小銭と何枚かの札が入っていたが、誰かが
入れたものか、自分たちで入れたものかは分からない。伊藤さんがカセットテープを買っ
た。
私はといえば、別のグループが売っていたデビルスティックを買った。両手に持った細
い棒で、宙に浮いたスティックを落とさぬように回転させる遊びで、初めて見たものだか
ら欲しくなったのだが、あとになって、それがわざわざフランスから買って帰らなくても、
日本で簡単に買えるものだと分かった。
この町の歴史については何の知識もなかった私だが、アビニョンと聞けばやはり『アビ
ニョンの橋の上で』という歌が浮かんでくる。
アビニョンの橋の上で 踊るよ 踊るよ
アビニョンの橋の上で 輪になって 組んで ・・・
そこまでしか思い出さないが、たぶん小学校で習ったと思う。
そのアビニョンの橋、実際はサン・ベネゼ橋というそうだが、川の中ほどまでしかない
姿が有名で、写真では何度も見ている。
行ってみると、当たり前だがなるほど写真と同じだ。石造りの重厚なアーチ橋だが、そ
れが川の中ほどでぷっつりと切れ、その先がない。現代なら架橋工事が途中でストップし
てそのまま放置されたような按配だ。
本当の理由は無論そうではない。800年前の完成時には長さ920メートルの堂々た
る橋であったのが、ルイ8世の侵攻や洪水で度々破壊され、とうとうそのまま放棄されて
しまったのだそうな。
しかし今こうして眺めると、無用の長物となった橋が穏やかなローヌ川の水面に映り込
んで不思議な景観となり、まんざら捨てたものでもない。というより、これがなかったら
アビニョンを訪れる観光客もこれほど多くはならなかったのではないか、と思う。
夕方、アビニョン駅からフランス新幹線TGVに乗る。
TGVは日本の新幹線と張り合う超高速列車だというふれこみだったが、乗ってみると
シートは狭く、おまけにビニール張りでなんだかみすぼらしい。日本の新幹線は乗客の好
みの方向にシートを回転できるが、TGVにはそれもない。犬を連れて乗っている人もい
たりして、なんだか田舎の列車という感じだ。
スピードは、周りが広い田園地帯のせいか、とくに速いという印象もない。列車の走行
音はかなり大きいし、揺れもある。
夜8時前、パリのリヨン駅につき、そのままホテルに直行。
ツアーも10日目を迎え、この日は終日自由行動ということ。
となればやはりルーブル美術館は外せない。
今でも美術音痴の私であるが、それでも絵画にまったく関心がないわけではない。眼底
に焼き付いている絵もいくつかはある。
そんなきっかけを作ってくれたのがルーブルだ。10年も前にここで見たジェリコーの
『メデューズ号の筏』は衝撃的で、私はその後、職場の図書館に足しげく出入りし、画集
などを見るようになった。
あのときはツアーの悲しさで、ガイドの説明が終わると次の絵に移動しなければならな
かったが、それでも最後にミュージアムショップで30分ほど時間をくれたので、急いで
戻ってもう一度眺めた。
今回のツアーは美術巡りと銘打っての旅なのに、美術の殿堂であるルーブル美術館が行
程に入っていない。オランジュリー、オルセーといったフランスを代表する美術館も予定
されていない。
これはちょっと手抜きのようにも見えるが、実は考え抜いたプランだと思う。初めての
場合、ルーブルはあまりにも広すぎて主要な展示品を効率良く見て回ることが難しい。ガ
イドが簡潔な解説を加えながら見どころをちゃんと案内してくれるというのは有難いこと
だ。
しかし、今回のように美術巡りをうたったツアーでは、1作品の前に5分もいないで次
に回るという見方で満足する客は皆無だろう。自分の好きな作品の前で好きなだけ時間を
とる。その代わり他のほとんどの作品は見ずに終わる。そういうことを許すためには「終
日自由行動」というのは気の利いた行程だ。「行った」「見た」の旅行は別の機会でいい。
というわけで、なにはともあれ『メデューズ号の筏』に直行だ。
まずその大きさに圧倒される。縦 491cm、横 716cm というから畳20枚ほどになる。
全体に暗い色調の中に筏に乗って荒海を漂流する十数人の人物が描かれていて、その中の
何人かは既に息絶えている。生存者も多くは裸で、一目して遭難船からの脱出行であるこ
とが判る。
初めてこの絵を見たとき、私には何の前知識もなく、ただその絵に漂う極限の空気に圧
倒されただけであった。帰ってから美術書で調べてみると、描かれている内容は概ね次の
ようなことであるらしい。
1816年、フランス海軍のフリゲート艦メデューズ号がアフリカ西岸沖で座礁した。乗っ
ていた 400人のうちボートに乗れたのは 250人、残りは急ごしらえの筏に乗り込んだが、
その重さに筏は耐えられず、多くの人々が波に呑まれた。かろうじて生き残った人も飢餓
と渇きに襲われ、死者の肉を食べたり弱者を殺したりした。
生存者が15人に減っていた13日目、遠くに僚船アルギュス号を見つけた生存者は狂
喜して布を振るが、船は気づかず遠ざかってゆく。その絶望の様子を描いたのがこの絵で
ある。
この事件のとき24だったジェリコーはすぐにこれを画題に選んだ。
2年をかけて事件を詳細に調べ、何枚もの習作を描き、その段階で生存者への取材、死
体置き場や病院での観察、筏の模型製作等、異常とも思える執念を見せている。
その結果、本作では死者の肌色、死にかけた人の表情等、正視をためらうほどの質感が
表現された。
案の定、美術界の反応は称賛と非難が激しくぶつかり合った。これによりジェリコーは
国際的な名声を博し、ロマン派の先駆者と呼ばれるようになった。しかし世の無常という
か、脊椎結核を患い、32歳で早世する。死に際して「まだ何もしていない」と言い残し
たというから、その無念さは察するに余りある。
残念ながら、このロマン派というのがどういうものかを私は知らない。『メデューズ号
の筏』の画面構成についても詳しい解説があるが、どうもよく解らない。
ではあるが、この絵に対峙したときの感動は半端なものではない。後年、徳島市に世界
の名画を原寸大の陶板画で展示した大塚国際美術館というのができて、そこでこの『メデ
ューズ号の筏』を見たとき、複製と分かっていても本物に劣らぬ感動を味わった。
とにかく、この絵はすごい。この絵だけ見て退館したとしても、十分満足できるのでは
ないかと思う。

それに引き替え、『モナ・リザ』などはどうということもない。ふーん、というだけで
ある。
ダヴィドの『ナポレオン1世の戴冠』、ドラクロワの『民衆を導く自由の女神』、ヴェ
ロネーゼの『カナの婚宴』、等々、私のような美術音痴でも知らずしらず口を開けて見入
ってしまう大作を心ゆくまで堪能したあと、ルーベンスの部屋というのに入る。
ルーベンスというと、昔読んだ『フランダースの犬』に、主人公ネロがルーベンスの絵
の前で死んでゆくくだりがあって名前だけは知っている。
ネロが見た絵がルーベンスのどの絵なのか、とくに興味もなかったが、さてルーベンス
の部屋に入ってみると、とても少年が憧れるような絵ではないと思った。神話に題材をと
ったらしい登場人物の多くが裸で、男も女も隆々たる筋肉をしている。
こんな、ある意味グロテスクな絵をネロは見たかったのだろうか。
帰国後私はもう一度調べてみた。ネロが見たのはルーベンスの『キリストの昇架』とい
う絵で、それはルーブルにあるものとは違って神秘的な絵であった。
私だけいったんホテルに帰り、伊藤さんとはオランジュリー美術館で落ち合う。言わず
と知れたモネの大作『睡蓮』の大壁画を見るためである。
その『睡蓮』は2階にある。楕円形の展示室の白壁いっぱいにその連作がはめ込んであ
り、その他には何もないという、なんとも贅沢な空間だ。絵は縦2メートル、幅20数メ
ートルといったところだろうか。それが部屋に4枚、そして同じ作りの部屋が2つある。
モネは印象派の大画家ということ。ここでも恥を晒すが、印象派というのが何であるか、
私は知らない。写実的に描くことよりも受けた印象を表現する手法をとるというのだが、
印象を表現するというのが解らない。
小学生のとき、図工の時間に写生をした。先生からこの絵の中心は何かと訊かれたが、
中心という言葉を真ん中という意味だと思った私は「この電信柱」と答えた。先生は、そ
んな中心があるかと言った。
また中学校ではよく、「感じたままを描け」と言われた。感じたままとは何なのか、そ
れをどう描けばいいのか、いまもって解らない。
とはいえ、折角パリに行き、印象派の代表作を見るというのであるから、私も多少予習
はした。
その中で、印象派の手法として、ある色を表現するには絵具を混ぜ合わせるよりも純色
の班を並べて、離れて見る方が鮮やかな色が見えるという視覚の癖を利用するのだという
ようなことがあった。
この説明は具体的なので、私もなんとなく解ったような気になり、『睡蓮』に近づいた
り離れたりしてじっくり見た。そう思って見ればそう見えなくもないが、本当のところ、
よく解らなかった。
解らないけど、なんだか良いものを見たという満足感で美術館を出て、コンコルド広場
で休憩。セーヌ河沿いに歩いてノートルダム寺院に行く。ここはパリで最も好きな場所で
あるが、その理由は塔のあちこちにあるガーゴイルにある。
ガーゴイルと当たり前のように書いたが、実はこの言葉は、初めてノートルダム寺院に
行ったとき、その奇怪な姿に魅せられて急ぎ調べて知った。
機能としては雨樋であるが、多くは動物の形をしており、雨水を口から排出するように
作られている。その動物は古代エジプトではライオンであったり、中国では龍であったり
するが、中世以降のヨーロッパでは悪魔や架空の動物などグロテスクなものが多い。
ここノートルダム寺院のそれはとくに奇怪で、映画『グレムリン』に出てくるような有
翼の怪物や、人とも動物ともつかぬ面妖なものがパリの街並みを見下ろすように並んでい
る。
11日目、美術巡りも今日で終わる。明日は朝のうちにパリを出て、日本時間の明後日、
成田に着く予定になっている。
ということで、最後のバス観光に出る。まずはルソーのアトリエというのに行く。とい
っても、実は何も覚えていない。今この稿を書くにあたっては旅行中につけていたメモを
見ているのだが、記述は「ルソーのアトリエ見学」とあるだけで、感想も書いていない。
ルソーといえば社会契約説で知られる政治思想家ジャン・ジャック・ルソーしか知らず、
画家の名としてはそのとき初めて聞いたのだと思う。アンリ・ルソーというのだそうで、
その日の午後美術館でその絵を何点か見た。なにやら不気味で、森の中で動物がこちらを
窺っていたり、なぜか裸婦が動物に囲まれていたりで、どこがいいのかさっぱり解らない。
それにしても、折角行ったアトリエについてまったく覚えていないというのはどういう
ことだろう。
ルソーについての関心の薄さと記憶力の減退がそうさせたのだろうが、とくに近年記憶
力の減退については絶望的な実感をもっている。以前も時間の経過とともにいろいろなこ
とを忘れていたが、それでもメモや写真を見ればそのときのことがかなり詳しく思い出さ
れたりしていた。
それが最近は、メモを見ても話を聞いても「そんなこと、あったっけ?」ということが
多い。やけに詳しく覚えていることと、まったく思い出せないこととがはっきり分かれて
いる。
たとえば、ルソーのあとに行ったミレーの家というのは、メモを見るまでもなく、はっ
きり覚えている。
フォンテーヌブローの森を抜けて行くとバルビゾンという村がある。通りに面して石積
みの小さな家が並ぶ落ち着いた家並みの中に、ミレーの家はある。「Maison de Millet」
と書かれた小さなプレートが壁に掛かっているが、それがなければただの家で、通りすが
りに見つけられるようなものではない。
中には『落穂ひろい』ほかミレーの代表作の複製画が何点か飾ってあるが、それはなに
か観光客用にとってつけたような感じで、いただけない。日本語の説明書も貼ってありム
ードを壊すが、それによると、ここバルビゾンにはミレーやコローをはじめとする風景画
家たちが集まって森や田園の風景を盛んに描いていたそうで、その画家たちはバルビゾン
派と呼ばれて高い評価を受けていたらしい。
そういえばバルビゾン派という言葉は聞いたことがあるが、それがどういうものなのか
ということは知らなかったし、調べようとも思わずにいた。それなのに、今なんとなく解
ったような気になっているというのは、やはり現地の風景と絵の中の風景が重なって、さ
らにフォンテーヌブローという、これは私も少しは知っているナポレオンゆかりの地にい
るという高揚感が相まってのことであろう。
午後はまたどこかへ行くことになっていたが、私たちはオルセー美術館に行きたかった
ので、それには参加せず、自由にさせてもらう。
3年ほど前に駅舎を改造して作られたということだが、1848 年 から1914 年までの美
術品を一括して展示しているらしい。ルーブルにあった多くの作品もここに移してあると
いうことなので、行ってみる価値は十分にあると思った。
なるほど展示空間はいかにも駅舎で、吹き抜けになった空間に2階ギャラリーがあり、
見て歩きながら気がつくと、いつの間にか駅を一周するような按配になっている。
アングルの『泉』、マネの『笛を吹く少年』はひときわ目を惹く。誰でも目にしたこと
のあるその絵は想像していたよりやや明るい色調だったが、旧知の人に会ったようにしっ
くりとこちらの感覚に入り込んでくる。
それはすばらしかったが、私にはルノアールの『ムーラン・ド・ギャレット』が強く心
に残っている。絵のタイトルは知らなかったのだが、絵そのものは画集などでよく見るも
ので、青味がかったその画面に描き込まれた大勢の人々は、ルノワール独特の首をかしげ
た動きで記憶に残っている。
その他ここで見た絵を羅列していたらきりがないので省略するが、見て回っているうち
に疲れてもきた。
そんなとき、1枚の鮮やかな絵が目に飛び込んできた。なぜか大海原の波の上に裸の美
女が横たわり、その上に数人の天使が舞っているという、意味の解らないものであるが、
その美女の裸身がなんとも美しい。
私は伊藤さんに「この絵、いいねえ」と言った。「こういう絵にすぐ目がいくのは、俺
の悪いところかなあ」とも言った。
伊藤さんは、そんなことはない、これはカバネルの『ヴィーナスの誕生』だ、と言った。
カバネル? 聞いたことがない。100年前のフランスの画家だそうで、作品には裸の
女性が多く出てくるらしい。

知らなかったし、その後もカバネル
について調べたことはないが、なには
ともあれ、この絵はかなり鮮やかに記
憶に残っている。
そしてこれが今回の美術巡りツアー
の締めくくりであった。
思えばこの旅行ではずいぶん沢山の
絵を見た。彫刻も見た。そして画家た
ちの足跡をたどり、名作の生まれた地
の風景を見た。
それでいながら美術に関する造詣が深まったわけでもなく、まして感性が磨かれたわけ
でもないのは情けない限りだが、まあ、そんなものか。
なにしろ生まれ育った環境は極めて散文的であったし、長じても日々雑事に追われ、時
間をかけて絵画に親しむというようなゆとりがなかった。いまさら優れた芸術に接しても
それを吸収する素地が育っていないということであろう。
ではあるが、そんな私にとっても今回のように集中して美術作品とその背景を訪ね歩く
という経験は、少なからず刺激的であった。前にはただ「見た」だけの作品が今回は「物
語」として見えたり、画面の一隅に作者の心血を感じたりもした。
やはり優れた美術作品というのはまず見ることが大切であり、さらに何回も見るという
ことが大切であると思い知らされた。芸術音痴の中年男が場違いな聖地で恥を晒し続けた
旅であったが、自己満足という意味では、これ以上はない旅であった。
同行してくれた伊藤さんにしてみれば、私のような貧にして鈍なる感覚しか持たぬ者と
連れ立っての美術鑑賞は以後願い下げというところであろうが、まあ、もう一度迷惑をか
けることはなかろうと思う。わずかな年金の中から税金や介護保険料などを容赦なく引か
れている今、美術館巡りなどという贅沢な旅は望むべくもないからである。
| ヨーロッパ美術巡り(3) | 一度かぎりの出会い | ||