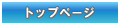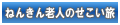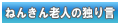台湾大名旅行(1)
ゆえなき接待に恐縮、また恐縮
1986年夏、親しくしているスポーツ用品店の店主、平井さんから台湾旅行に誘われた。
どういう縁か知らないが台湾に知り合いがいて、ときどき遊びに行くのだとのこと。飛行機とホテルだけ自分で払えば、観光や食事はその知り合いが持ってくれるという。
そういう旨い話を逃す手はないから、ホイホイと誘いに乗った。
台北の空港。現在は台湾桃園国際空港という名になっているが、当時は中正国際空港といった。以前乗り継ぎで何度か立ち寄ったことがあり、いつもミリタリールックの係官が厳しい口調でチェックをしていた。
だからちょっと緊張したが、案に相違して入国審査でも税関審査でも何も聞かれず、拍子抜けする。
ロビーにはその知り合いという人が迎えに来ていた。ずんぐりとした中年の男性で、名前は楊さんといった。ヨウさんと発音するのではないらしいが、ヨウでいいと笑っている。平井さんもヨウさんと呼んでいる。
ほとんど不自由なく日本語を話し、よく笑う。「そうですか」というのが口癖だ。
いくら世話になるとはいえ、まったくのタダというわけにもいくまい。滞在中1回くらいは夕食をこちらで持つ必要もあろうから、多少の台湾ドルは用意しておきたい。
そう思って両替所に行こうとすると、平井さんに止められた。ホテル代はクレジットカードで払えるし、それ以外には使うことがないという。
そうは言っても・・・と困っている私に頓着なく、平井さんは車に向かって歩き始めてしまった。
小一時間で台北市内のホテルに着く。途中いくつか由緒ありげな建物があり、質問もしたかったのだが、平井さんと楊さんの世間話には切れ目がなく、質問の機会はまるでなかった。
荷物を置くのもそこそこに、ロビーで待っていた楊さんの車で観光に出る。
最初に行ったのは忠烈祠という場所だった。緑の瓦屋根が3基連なり、白壁にアーチ型の入口が3つ並んだ壮麗な門をくぐる。
白く舗装された広場を隔てて2層の瓦屋根をもった巨大な建物が見える。瓦はオレンジ色、列柱は赤。なにやら厳かな空気に圧倒されながら本殿に向かうと、そこにはベージュ色の制服を着た兵士が2人、向かい合って立っている。ベージュの制服は陸軍のものだそうだ。
ここは過去いくたびかの戦争で亡くなった人々の英霊が祀られているのだそうで、兵士は大門と本殿を守るため2人ずつ立っているとのこと。
ほどなく先ほど通った大門から青い制服の兵士が5、6人入ってきた。隊列を組み、一糸乱れず颯爽と歩いてくる。これは空軍だとのこと。
その格好良さに見とれていると、本殿の前でそれまで立っていた陸軍の兵士との交代式が始まった。銃を回したり互いの位置を交代したり。よくもまあというくらい動きが揃っていて、こちらは思わず息を吞む。
ただ、いささか長すぎる。動作の一つひとつには、例えば銃の点検というような意味があるのだろうが、それが観光客を意識したショーになっていて、そのため不必要な動作が加わってしまい、くどくなっているのだと
思う。
 |
| 衛兵交代 (楊さん撮影) |
それでも、終ってベージュの制服の
兵士が帰ってゆく行進はまたすばらし
い。
体が上下に動かず、脚を見なければ
スケートで移動していると思っても不
思議ではない。どこかの国の軍事パレ
ードなどでぴょんぴょん跳ねるように
歩いている滑稽な動きとは大違いだ。
さて新たに立ち番についた兵士はと
いうと、これまた世界各地の衛兵がそ
うであるように、何があろうとも微動
だにしない。観光客がキャーキャー言
いながら並んで写真を撮ったりするが、ピクリとも動かない。
そばに別の兵士が控えていて、汗を拭いてやったりしている。これは衛兵が動かないことを見物人にアピールするための演出であろうが、どう見てもわざとらしさが鼻につく。
域内には鐘楼、鼓楼などもあり、緑の瓦に赤の柱がいかにも中国らしい雰囲気を醸し出している。台湾に着いた日に早速このような場所を見学させてもらったのは実にありがたいことで、外国に来たという実感を十分に味わった。今回の旅行にカメラを持ってこなかったのが返す返すも残念でならない。
次に連れて行かれたのは迪化街という所で、建物が皆3階建てぐらいなのと夥しい数の看板が掲げられているのを除けば、上野のアメ横のような雰囲気だ。行き交う人々の多いのもアメ横と同じ。
漢方薬と乾物を売る店が多い。2、3軒、覗いて歩く。客と店員との会話は喧嘩でもしているように早口で、無論、何を言い合っているのかさっぱり解らない。それにしても台湾の人はこんなに薬を飲むのだろうか。目方で買っているようで、紙袋にごそっと詰めて持ち帰る。
楊さんは私に、漢方薬が要るなら通訳をするから何でも聞いてくださいと言ったが、通訳してもらうまでもなく、店員はかなりの日本語を話す。折角ながら私は薬にまったく興味がないので、ただ店内の雰囲気と、出入りする人々の活気に圧倒されて立ちつくしていた。
平井さんはさっさと店の一角にあるテーブルに向かい、店員が心得たようにお茶を出す。そこでも平井さんと楊さんは薬にも観光にもまったく関係のない世間話に興じていて、いったい何のために台湾まで来たのかと思ってしまう。
といって、楊さんは私をほったらかしにしているというわけでもなく、平井さんとの世間話の最中に唐突に私に向かって、夕飯は何が食べたいですかというようなことを訊いたりする。店員も沢山の客がいて忙しいにも拘わらず、何かと話しかけてきて、それはそれなりに楽しかった。
いったんホテルに帰り、シャワーを浴びて待っていると楊さんが夕食の迎えに来た。
車が着いた所は大層なレストランで、店構えの立派さにまず驚く。こんな所に来るのなら、もうちょっときちんとした格好をしてくればよかったと思う。なにしろ私は台湾に誘われたときから勝手な先入観を抱いており、食事は屋台か大衆食堂のような所でするものだと思っていたから、きちんとした服は持ってきていない。
もっとも楊さんも平井さんもポロシャツで、とくに改まった服装ではない。
客席の間をかなり歩いて個室に案内されると、そこには恰幅の良い年配の男性と、いかにも人の良さそうな太ったおばさんがいた。ほかに40代と思われる男性が1人。
年配の男性は小さな会社の社長らしく、おばさんはその人の奥さんであった。この社長はやはり楊さんという名であったが、我々を世話してくれている楊さんとは親戚でも何でもなく、ただ偶然に同じ名前だということだった。聞けば「楊」という姓は台湾ではごくありふれたものらしい。
驚いたことに全員日本語を話し、上手下手はともかくとして、私が会話に困るということはなかった。こんなにも日本語が通じるということは日本による統治のなごりで、こちらとしては後ろめたい気分にもなる。
豪華な料理が次々と運ばれてくる。銘柄は分からぬがビールも美味く、知らず知らず食が進む。
紹興酒も出た。見ているとグラスを持っていない方の手をグラスの底に軽く当て、一気に飲み干す。まあ小さなグラスなので難なく飲めるし、口当たりもいいので私も同じように飲んだ。
面白いのは一々乾杯することで、誰かが音頭をとり、全員がグイッと飲む。一口で飲み切らなければならないとかで、空になったグラスの底を見せ合う。
誰もが打ち解けた態度でおおいに喋り、おおいに笑い、私もくつろいだ気分で飲み食いをしていた。
料理は更に次々と運ばれてくる。鶏の足も出てきた。醤油で煮たものなのか真っ黒で、形はそのまま。それが大皿に山盛りになっている。勧められたが、これはさすがに手が出ない。社長夫人はあっけらかんとした態度でそれを手で持ち、かぶりつく。骨を載せる皿があり、それが見る見る山になっていく。
話の端々で察するに、社長は平井さんと商売上の取引があるらしく、平井さんはいわば客で、この席はどうやら接待ということのようだ。ということは、私はご馳走になるいわれがないのだが、皆そんなことはおくびにも出さず、まるで旧知の間柄のように接してくれる。
私もいい気になって飲み食いをしていたが、間断なく繰り返される紹興酒の乾杯でかなり酩酊し、自分でもろれつが怪しくなってきたのが分かる。
さてようやく食事が終わり、会計という段になった。ウエイターが何枚もの伝票を持ってきたが、それぞれにかなりの料理名が書かれているらしい。
そしてここからがなんとも理解しがたいのだが、社長と奥さんはその一品々々をテーブルの皿を見ながら確認し始めた。むろん既に片付けられた皿もあるのだが、それについてはウエイターを呼び、なにやら聞いている。これは中国語なので、こちらには解らぬが、様子から察するに、「これは本当に食べたか」というようなことを聞いているようであった。
とにかく一品々々である。相当な飲食をしているからその数も量も半端ではない。酒だって何本飲んだか分からない。
結局伝票記載のものはすべて確かに飲み食いしたということが確認できて、支払いも済んだのだが、これは日本人には理解できない。日本では請求された金額をそのまま払うのが普通であるし、仮にちょっと請求額が多いかなと思っても、客の前で一皿々々確認したりはしない。
私は自分が調子に乗って酔っ払うほど飲食したことが申し訳なくなり、気まずい思いに襲われた。平井さんは社長の確認作業中も楊さんやもう一人の男性相手に大笑いしながら雑談をしている。相当な神経だ。
ホテルに帰ってから平井さんに、全部向こうに払わせたのはまずかったのではないか、と言った。
あれは社長がケチだとか金額が高いとかいうことではなく、台湾では普通の習慣なのだという返事だった。日本人のように見栄を張って相手の言いなりに払う方がおかしいのだとも言う。
まあ、そうではあるが。
翌朝、けたたましいベルで飛び起きた。受話器を取ると、流暢な日本語でお客様がロビーでお待ちですと言う。慌てて身支度をして降りていくと、楊社長の奥さんが待っていた。朝食の迎えに来てくれたとのことで、昨夜食事をしながらそういう約束ができていたらしい。
ありがたいが、まだ顔も洗っていない。とりあえずフロントから平井さんの部屋に電話をしたが、出ない。おかしいなと思ってフロントに聞いてみると、平井さんのキーはフロントにあった。いつの間にか出かけていたのだ。
しかたなく社長夫人に待ってもらって、ともあれ洗顔だけは済ませる。
玄関にはタクシーが待たせてあったようで、夫人は助手席に乗ると運転手に何やら言った。そして後ろを向いて、お寺にお参りしてから行きましょうと言う。台湾のお寺というのも興味をそそられる。
着いたところは孔子廟という所だった。お寺というから楊家の菩提寺だと思い、理由もなく小さなお寺だと思い込んでいたのだが、孔子様を祀ったところだとは驚いた。
タクシーを降りるとそこはもう入口で、孔子廟というにしては地味なものであった。長崎の孔子廟の方が華やかだ。
中には緑の濃い庭園があり、それを抜けると初めて「孔子廟」という文字が出てきた。いやそれは嘘で、実際には「孔廟」と書かれている。本堂は特に巨大というわけではないが、2層の反り返った屋根、龍の彫刻が施された太い柱など見ごたえのある造作で、人々の思い入れが感じられる。
内部は赤を多用した壁面が参拝者を圧倒している。真っ赤でありながらケバケバしさはなく、並べられた位牌と相俟って見る者の居ずまいを正さずにはおかない。仰ぎ見るとまた見事な極彩色の丸天井で、これまた息を吞む。
天井と書いたが、今思うと、半球型の天井というのは屋根の形に合わない。あれは天井ではなくて天蓋だったかも知れない。肝心なところで記憶が不確かなのは我ながら情けないが。
建物はかく立派であったが、それ以上に胸を打たれたのはお参りの人の多さとその態度だ。老若男女入れ替わり立ち替わり本殿にお参りしているが、どの人も見るからに心を込めているのが分かる。
4、50センチはゆうにあろうと思われる長い線香を数本持ち、それを額の前で押しいただくようにして、長々と拝んでいる。若い女性も多く、真剣な態度が見てとれる。出勤の途中でお参りをしていくらしい。
日本では若い人はあまりお寺に行かないし、たまに行っても賽銭を投げ入れて形式的に手を合わせ、ちょこんとお辞儀をして終わりだ。
私もせめて線香ぐらい上げようと思ったが、このときになっても私はまだ台湾ドルを持っていなかった。日本円で買えるとも思わなかったが、ともあれ線香を売っている所に行って思案していると、妙なことに気付いた。
次々と線香を受け取って本堂に向かう人たちが、誰一人としてお金を払わないのである。
しばらくして、これはタダなのではないかと思った。そこでおずおずと近づいて行くと、売り場のおばさんが極く当り前のようにして私に線香を渡してくれた。お金を要求する様子はさらさらない。
とまどいながら「謝々」とか言って貰ってしまった。
さて、貰ったはいいが、どう上げていいのか分からない。見ていると参拝客は何本かの線香を持って何か所か回り、それぞれに1本か2本ずつ上げているらしい。
私も周りの人の真似をして線香を上げ、一応拝んでみたが、我ながら形ばかりで、なにか申し訳ない気分にもなる。
それでもこれまでお寺の参拝で感じたことのなかった満ち足りた気分になり、台湾という国はたいしたものだと感嘆した。
待たせてあったタクシーでレストランまで行く。大きなレストランで、朝というのにほぼ満席であった。予約してあったらしく、奥の席に案内される。
幸いメニューは写真つきで、私はお粥と饅頭を注文した。奥さんは麺をとり、私にもどうかと勧めたが、中国料理の麺はどうも口に合わない。ラーメンがあれば別だが、日本のラーメンは中国料理とはまったく別のものだそうで、扱っている店はない。
お粥はすこぶる美味い。お粥というと、私などは病人が食べるものだとしか思っていなかったが、前年中国に行った折り、団体旅行であったからメニューはすべて手配済みで、好むと好まざるとに関わらずお粥が出た。これが滅法美味くて私は認識を新たにした。
そんなわけでここ台湾でもお粥にしたのだが、期待どおりで言うことはない。ただ腹持ちがしないような気がして、饅頭を4、5個食べた。といっても1個が大福ぐらいの大きさだから、とくに大食いをしたということでもない。漬物のようなものも何皿か出されたが、それもあらかた食べてしまった。
社長夫人はホスピタリティーに溢れた人で、朝食の間もあまり上手とはいえない日本語で次々と話題を提供してくれる。もっとも、上手ではないというのは勝手な話で、私は一言も中国語を話せないのだから、夫人の日本語は有難いことこの上もない。
今日は台北市内を案内してくれるとのこと。どこか行きたい所はあるかと訊かれ、私は「小人国」に行きたいと言った。世界各地の観光名所を25分の1のミニチュアで展示しているところで、日本では東武ワールドスクェアが知られている。
もっともこのときはまだ東武ワールドスクェアはなかった。オランダのマドローダムが有名であったが、この時点で私はまだオランダに行ったことがなく、つまりミニチュアワールドというのは見たことがなかった。
台湾にそれができたのは、この旅行の2年前で、是非とも行ってみたいと思っていたのである。
楊夫人はちょっと意外だという顔をしたが、快く承知してくれた。結構距離があるので、このまま行きましょうということで、レストランでタクシーを呼んでもらい、そのまま出発した。なるほど遠く、高速道路で1時間以上かかり、ようやく小人国に着く。
1時間も乗ったのだからタクシー代は相当な金額になったと思う。今朝の食事といい、このままでは申し訳ないので、せめて小人国の入園料は払おうと思った。台湾ドルはまだ持っていなかったが、カードで払えるだろう。
ところが夫人は「トンデモナイ、トンデモナイ」と日本語で言い、私を押しのけてチケット売り場に行った。
入園券を受け取りながら私は恐縮ついでに、平井さんに連絡をとりたいのでチケット売り場で電話を借りてもらえないかと頼んだ。夫人は、どうせホテルにはいないからあとにしましょうと言って取り合ってくれない。どうも夫人は平井さんの行き先に見当がついているのではないかと思った。
小人国は実に面白い。ガリバーになった気分だ。後年オランダのマドローダムにも行き、日本の東武ワールドスクェアにも行ったが、どちらも「ああ、小人国と同じだ」と思ってしまったくらいである。ここでもカメラを持たずに来たことが悔やまれる。
台北に帰ったのは午後もかなりの時間になっていたが、昼食をとることになった。
といっても時間が時間であるし、本格的な料理ではなくて飲茶にしようということであった。飲茶と言われてもどういうことか私には分からなかったが、お茶を飲みながら点心を楽しむということらしい。
いろんな種類のお茶が出て、どれも日本のお茶ほど美味くはなかったが、まあ珍しいので楽しむことはできた。小さなセイロに入った点心を満載したワゴンがテーブルの間を回ってくる。私も適当に2、3の餃子や包子などを取ったが、夫人は次から次へとセイロを取って私に勧める。どれも美味くてかなり食べたが、ビールならぬお茶では、だんだん腹ががもたれてくる。
せっかく夫人が取ってくれたセイロが手つかずで残っているものもあった。謝ると、手をつけていないものは勘定されないのだという返事であった。本当かどうかは分からない。
ホテルまで送ってもらって社長夫人とは別れたが、結局この日の食事、タクシー代、小人国入園料、すべて夫人が払ってくれた。
前述のとおり私は誰と商売をしている訳でもなく、接待を受ける立場ではないので、思いは複雑・・・というより、正直なところ負担であった。
腹も膨れていて、疲れてもいた。ベッドに仰向けになるとそのまま眠ってしまった。
ノックに起こされると、平井さんだった。
私が一日どう過ごしたのか、聞こうともしない。自分がどこに行っていたのかも言わない。ごく当たり前のように、さあ飯を食いに行こうと言う。磊落な人柄が魅力で平素から親しくしてもらっているとはいえ、掴みどころがないのも事実だ。
ロビーで、社長ではない方の楊さんと前夜の食事で一緒だった40代くらいの男性が待っていた。男性は謝さんといったが、社長でない楊さんとどういう関係なのか、社長の楊さんとの関係はあるのか、分からない。
思えば今回台湾で世話になった人たちは皆、自己紹介で名前は言うものの、身分や間柄などについては何も言わなかった。私のことも名前を聞いただけで、それ以上のことは何も尋ねない。平井さんも私が何者なのか紹介もせず、私としては初めのうち居心地が悪かった。
楊さんが、何を食べたいかと訊く。実はあまり腹が減っていないのだと言うと、例によって「そうですか」と言い、それでは街を見物してから食べに行きましょうとのこと。
楊さんの車で出る。町中看板だらけだ。その中に「○○中心」という文字がやたら目につく。「△△薬中心」というのもあった。私は薬を主に、つまり薬を中心に売っている店なのかなと思った。「健康中心」というのは何だろう。健康を主に扱っている店というのでは意味が通じない。
謝さんに訊いてみた。なんと、「センター」だという。英語の center をそのまま訳したものなのだ。まあ、カタカナがないから無理やり漢字にしたのだろうが、せめて音(おん)を当てて仙太とでもしてほしかった。現にコカコーラは可口可楽となっているのだから、英語の音を漢字で表す方法はあると思うのだが。
着いた所は衣料品の問屋街ということだった。問屋といっても、一般の人も買える。
どう表現したらいいか分からないが、無理に例えれば焼津の魚センターで商品を魚から衣料品に変えたら雰囲気が似てくるだろうか。
道の両側は小さな店がびっしりと並んでいて、とにかく狭い。すれ違う人とぶつかりながら歩く。
様々な原色の生地や服で店員の姿も隠れてしまうほどだ。道は縦横に入り組んでいて、自分が今どっちに向かって歩いているのかさっぱり分からない。楊さんたちを見失っては大変と思い、服を見るどころではない。
ときどき、日本語での呼び込みがある。アクセントも自然で、とかく外国の観光地で聞かれる変な日本語ではない。謝さんが何度か立ち止って私にこういう服はどうですかというようなことを訊くが、あいにく私は服に興味がないので、ただ喧騒に包まれた雰囲気を楽しむだけで十分であった。
そのまま歩いていくと、今度は急に薄暗い路地に出た。道幅は3メートルそこそこで、両側の店が商品を載せた台を路上に置いているものだから、ほとんど道はないと思っていい。
少し行くと、道に大きくせり出した台の上に鉄製の籠がいくつも積まれた店があった。一目でその籠の中に蛇がうじゃうじゃと入っているのが分かり、総毛だって足が止まった。
平井さんが振り返り、早く来いと手招きをする。冗談ではない。
「大丈夫だよ。出やしないから」
そういう問題ではない。蛇などという邪悪な生き物のそばを通り抜けなければならぬいわれが、どうしてこの私にあるのだ。
地球上には人間によって絶滅に追い込まれた生物が数限りなくいるという。ならばもう一種類、すなわち蛇というものを絶滅させたって特別罪が深くなるというものでもあるまい。
平井さんの顔に本気で私を置いて行こうという気配を感じたので、私は蛇屋の向かい側の店に入り、商品の裏を通って道の先に出た。しかし、蛇屋は何軒もあり、中には干乾びた蛇を束にして軒先に吊るしてある店もある。店員が生きた蛇を手に持って通行人に勧めている店もあり、私は本気で怒って店員を怒鳴りつけた。
道を開けろ! 店に引っ込め!
ところがそういう店に限って日本語が解らないらしく、店員は笑うばかりで、こともあろうに私に近寄って来ようとさえする。
そんなこんなで平井さんたちを見失ったと思ったとき、ある店の中から平井さんが呼ぶ声がした。狭い間口に例の籠が積んであり、くねくねと蛇がうごめいている。私は道路に立ったまま待っていた。
楊さんがプラスチック製の四斗樽のようなものから柄杓で酒らしいものを汲み、コップに注いで飲んでいる。
そのプラスチックは薄いらしく、不明瞭ながら絡まった紐のような物体が透けて見える。それが蛇であることは聞くまでもない。楊さんがコップを揚げて私にも飲めというジェスチャーをする。
無論応じるわけもなく、そのまま待っていると、しばらくして3人が出てきた。楊さんが笑いながら言った。
「飲んだ方がいいですよ。今晩ビンビンですよ。1人じゃ眠れませんよ」
なんでそんな日本語を知っているんだ。
そのあと別の場所で夕食になったが、何を食べたのか覚えていない。というより、すっかり気色が悪くなって、ほとんど何も食べなかったのではないかと思う。
| 心痛む中国の旅 | 台湾大名旅行(2) | ||
| 5月中旬更新予定 |