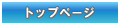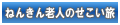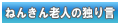二日酔い反省、荘厳なミサ
ケルン大聖堂で居ずまいを正す
ケルン大聖堂。世界史の教科書に必ず写真が載っている、ゴシック建築の代表的な教会である。
2010年の6月、ちょうど30年ぶりに再訪することになった。今回は妻と一緒だ。
私は42年間好きな仕事を続け、土日も祝日も仕事優先という日々を送ってきた。だから退職後は妻への罪滅ぼしをせねばと思っていた。
退職の直前、娘が結婚した。相手は重盛君といい、ドイツのメーカーで工業製品の研究開発をしている。結婚式のために帰国したものの、式を終えるとすぐにまたドイツに戻った。娘はその3週間後、受け入れ準備の整った新居にちゃっかりと収まった。
さて妻への罪滅ぼし。まずは旅行と考えていたが、なかなか具体的に検討できずにいた。なにしろ40年以上も勤めたので、残務整理が簡単には終わらない。あっという間に1年が過ぎた。
ところが、その間に妻はどうやら娘とメールのやりとりをしていたらしく、ようやく私が雑用から解放されたのを見て、ドイツに行こうと言い出した。
他家に嫁いだ娘を追いかけて行くようで男としてはあまり格好のいい話ではないから、私は気が進まなかったが、重盛君からも是非にと誘われているという。
まあそれならとも思うし、そもそもこの旅行は妻のためであるから、私も折れた。
とはいえ、行けばなにかと負担をかけることは避けられないから、なるべくそれを少なくするため、滞在型ではなく、周遊の途中で立ち寄って1日か2日を過ごすということにしよう。ついては妻が行ったことのないオランダから回るというのはどうか。
妻は賛成したが、オーストリアのザルツブルクにも行って、サウンド・オブ・ミュージックの舞台を歩きたいと言う。私はそこまで行くならハルシュタットにも行こうと言い、テーマも脈絡もない継ぎはぎの案ができあがった。
負担をかけたくないという思いは伝えてあったのだが、重盛君は1週間も休みを取って我々を接遇してくれるという。それを知った私は、なんとしてもそれを止めさせようとした。男が私用で1週間も休むなどということをしたら、休み明けには自分のデスクに後任が坐っていることになる。
悲しいかな、そういう考えは日本の、それも古い世代のものらしく、ドイツでは年休消化は至上命令であり、部下が休みを取らなかったら上司の失点になる。ゆえにみな、年休を消化するために四苦八苦しているのだという。
まあ、今から思えばそれは私たちの心理的負担を和らげるために誇張して言ったことなのだろうが、そのときは愚かにもそれを真に受けて、それならばという気になって言葉に甘えた。
その結果、娘夫婦はアムステルダムまで出てきて私たちと合流し、私たちは重盛君の車であちこち観光しながらケルンまでやってきた。
まずはホテルに入り、荷物を置いて早速大聖堂へ。
30年前のアルバムを見ると、写真に「ケルン大聖堂前、ハウプトバンホフ駅で」などという文字が添えられている。その駅の前で、あちこちにハウプトバンホフという駅があるけど、どういう意味かと娘に尋ねた。それは固有名詞ではなくて、「中央駅」という意味だと言われて思わず下を向く。どうりであちこちにある筈だ。
その中央駅前広場はケルン大聖堂の基台の階段につながっている。仰ぎ見ると高さ157メートルという尖塔の頂部に至るまで細かな彫刻でびっしりと埋められた石壁が続く。当り前ではあるが、それがコンクリートではないため、積み重ねた石の継ぎ目が生々しく見える。
正面からは見えない空中の梁もここからはよく見える。これはゴシック建築の特徴で、パリのノートルダム寺院やミラノのドゥオーモのものが有名だが、ここケルン大聖堂のものも決して負けてはいない。それぞれの梁に刺繍と身まごうような透かし彫りの襞がついていて、しかもそれらが石を繋ぎ合わせてできているのが見て取れて、いかにも人の手で作ったという感じがする。
正面に回ろうと、石段を上る。そこにびっくりするほどの大男が仰向けに寝ていた。シャツをたくし上げて腹をむき出しにしているが、カバが仰向けになったらこうなるだろうと思うほどの腹で、なにをわざわざそんな醜悪なものを人目に晒しているのかと思う。
見ると、その腹の横に金属製の皿が置いてある。してみると、その腹を見世物にしていくらかでも稼ごうという魂胆か。ただ寝ているだけでカネを貰おうとは不届き千万で、なんぼなんでもそんなことでカネを払う御仁がいるとも思えぬが、皿にはそれでもいくらかの小銭が入っている。まあ、自分で入れて“呼び銭”にしているのであろう。
正面に出ると、敷石に大きな絵が描かれている。軽くこすってみると指に黄色い粉がついた。すぐ消えるようにチョークの類で描いたのであろう。やはり皿が置いてあって、小銭が入っている。これなら分かる。

改めて大聖堂を見上げる。きざな言い方にはなるが30年ぶりの再会である。
その変わらぬ威容にこみ上げてくる感動を隠すのに、意味もなく敷石を足でこすったりして平静を装わねばならなかった。
辺りが次第に暗くなり、ライトアップされた双塔が夜空に浮かび上がる。単色で控え目な照明で、いやがうえにも荘厳な雰囲気を醸し出している。この辺りが無秩序に電球を飾り立てる中国のセンスと違うところだ。
聖堂からほど近い路地に「PETERS BRAUHAUS」というレストランがある。重盛君は前にも来ているということで、これぞドイツという雰囲気を味わえるらしい。
ドイツ語は全く解らないが、BRAUHAUS というのは英語の Brew と House を思わせる。つまり醸造所ではないかといい加減に考えながら入る。
醸造所に併設されたレストランというのはとんだ見当違いで、パブとレストランが一緒になった所といったらいいか、木をふんだんに使った、日本ならさしずめ「キッチン・ナントカ」とでも名付けられそうな趣きのある空間であった。
何組かの先客があり、我々は奥のテーブルに通された。
なにはともあれビール。銘柄が分かるわけでもないので、重盛君の勧めで地ビールを頼む。「ケルシュ」というのがケルン特産のビールという意味だそうな。
シュタンゲと呼ばれる細い円筒形のグラスに入ったビールが運ばれてくる。「Prost !」と言うのが「乾杯!」ということらしい。とにもかくにもグビッといく。すこぶる美味い。
グラスが細いのですぐ空になるが、注文もしないのに新しいグラスが運ばれてくる。ウエイターはその都度コースターに線を書き加えていく。それで客が何杯飲んだかが判るという按配だ。客はペースを落としたいと思ったら、コースターでグラスに蓋をする。また飲みたいと思ったら蓋を外す。蓋をしないと何杯でも運んでくるということだそうだ。
このコースターには「Prost, Prost, Prost」と書かれており、いやが上にも気分が盛り上がる。よく見ると「1847年にペーターとバンベックが創業した私家醸造所。この家にこのビールあり」というようなことが書かれているように思えたが、あまりに当てずっぽうなので重盛君に確認するのもはばかられ、話題にはしなかった。
メニューはもちろんドイツ語で、読めるわけもないし、そもそも日本語のメニューを読んでも皆目判らぬ料理音痴であるから、注文はすべて若夫婦と妻に任せる。次々と運ばれてくる料理はどれも申し分がなく、お約束の焼きソーセージやジャガイモは得も言われぬ。なにやらフライパンのまま出された野菜料理もあったが、このフライパンのままテーブルに出すというのは、ドイツではごく普通で、魚料理などもあるらしい。
とにかく肉も魚も美味い、ビールも美味い。というわけで私はすっかり酔い、あげくにとんでもないことを口走った。
「いやあ、いやあ、今夜は楽しい。料理は美味いし、ビールは美味い。こんなに楽しい夜を設定してくれた重盛君に感謝、感謝! ついてはここの会計もすべて重盛君に任せよう!」
妻は「そんな・・・」と言って止めたが、重盛君は「そう言っていただければ、お連れした甲斐があります」と言って、全部払ってくれた。
あとで娘が撮った写真を見ると私の顔は真っ赤で、あれは多分「いい気なもんだ!」と思った娘が後々の証拠として撮ったのに違いない。
翌日はケルン大聖堂の南塔に登る。
娘夫婦は、私は絶対に登れないと思っていたらしい。娘はその少し前にウルムの大聖堂というのに登り、その時のきつい記憶から、お父さんがケルンの大聖堂に登れるわけがない、と思っていたとのこと。
私は30年前に難なく登っており、今回もどうということはないと思っていた。しかし、娘夫婦にさんざん冷やかされ、あまつさえ妻までが「途中で死なれたら帰りが困る」と失敬なことをほざくに及んで、私は内心不安にもなってきた。
考えてみれば30年前とは体力が違う。最近は勤務先の階段でも息が切れる毎日を送っていた。509段を登り切れるか。
実は前夜のレストランでの話題も、専ら私が上まで登れるかということで盛り上がっていた。そんなに飲んで明日は大丈夫かとか、そんなに食べると体重が増えて明日の階段がきつくなるとか。あげくに、死んだら他人の振りをしてすばやく離れるという相談までしている。
3人はそれでおおいに笑っていたが、私としては大丈夫だという気持と、万一にもダメだったら男のメンツが立たぬという気持とが交錯して、心中穏やかではなかった。
さて登る段になって、皆は私が転げ落ちたら支えられるように後から登ると言う。失礼な話だ。
こうなったら皆を引き離して上で笑いながら待ってやる。そう思って登り始めた。下から娘が「お父さんの息づかいが荒いよ」などとからかう声がして、妻が大笑いしているのが聞こえる。私が壁に書かれた漢字の落書きを見て、これは中国人だなと言うと、それを私が休むための口実だと揶揄する始末。どこまでもふざけた連中だ。
狭い螺旋階段で窓もないので、あとどれくらいで上まで出られるのか見当がつかず、不安がよぎる。やはり前夜の飲み過ぎが響くのか、息が切れる。呼吸を歩調に合わせ、一定のペースを守ることでなんとか登り続けた。
幸い倒れもせず、死にもせず、なんとか鐘楼まで出た。壁中落書きだらけだ。前回も落書きの多さに呆れた記憶があるが、その後世界遺産に登録されたというのに対策は講じていないのだろうか。
そういえばドイツはどこに行っても落書きが多い。電車の窓から見ると沿線はさながら落書きのコンペティションだ。それに比べれば日本の暴走族の落書きなどは可愛いものだと思う。
その鐘楼からさらに上に登る鉄製の階段がある。周囲が丸見えなので高所恐怖症の人には登れないだろう。30年前はそれが階段ではなく、梯子だった。途中でうっかり下を見た私は足がすくみ、しばらく梯子にしがみついていた。その後は人目も何もあらばこそ、両腕で梯子を抱え込み、ほとんどいざるようにして上まで登ったものだが、今回は狭いながら階段になっているのでなんということもない。
“下界”に下りたときは宿題を終えたような開放感で、口笛でも吹きたいのをこらえて聖堂内部へ。ちょうど日曜日のミサが始まろうとしているところで、既にかなりの数の信徒たちが席についていた。厳かな空気が流れ、さすがに観光客も息を殺しているのがわかる。
赤い僧衣を着た、見るからに聖職者という男性が数人立っており、そこから先に野次馬たちが入らないように牽制している様子。別に信者でなくても入れるのだが、観光気分で騒ぎながら入ったりする者、あまりにだらしない服装の者などは注意をするのだろう。
私もよもやとは思うが、酒の匂いなど残っていてはまずいので近寄らず、有名なステンドグラスや横たわるキリスト像を配した献灯台などを見て回る。
ステンドグラスはゴシック建築に限ったものではないが、壁ではなく梁で建物を支える工法のせいで、ゴシック教会は高窓に光がよく当たる。そのためステンドグラスの美しさが際立ち、ステンドグラスというとゴシック建築の専売特許のように思われている。
わけてもこのケルン大聖堂のものは精緻な宗教画でつとに知られており、訪れる誰もが忘我の面持ちで仰ぎ見ている。
祭壇に向かって右側の窓にはめ込まれたステンドグラスはバイエルン王ルートヴィヒ1世から贈られたものだそうで「バイエルンの窓」と呼ばれている。30年前にガイドさんが詳しく解説してくれたおかげで私は新約聖書にかなり興味を持ち、信者ならぬ身にしてはよく読むようになった。
今また、そのときのままの絵を仰ぎ見て、いささかの興奮を覚える。キリスト生誕に際し東方の三博士が贈り物を持って訪ねてきたという場面。聖母マリアがキリストの遺体を膝に載せて我が子の死を悲しむ、いわゆるピエタ。福音書を書いたマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4人の全身像。そして聖ステファノがエルサレムのユダヤ人たちの石打ちの刑にあって殉教する場面。
信仰心の有無に関わらず、見る者は居ずまいを正さずにはいられない。二日酔いのまま仰ぎ見るなど、もってもほかである。
柄にもなく心を洗われた気分で外に出ようとすると、出口に男が3人、べったりと坐っている。
なにをするでもなく、ただ坐っているだけで、前に皿が置いてある。働けないような年寄りならともかく、20代か30代と思われる若い男もいる。
昔日本にも傷痍軍人というのがいて、戦闘帽に白衣という格好で通行人に恵みを乞うていた。戦争で負傷し、働くに働けない人たちである。冷静に観察すると、戦争当時子供だったのではないかと思われる年齢の人もいたし、とりたてて怪我をしているようには見えない人もいた。
それでも、彼らはアコーデオンを弾くとか軍歌を歌うとか、なにがしかの努力をしていた。
ここ大聖堂の前に坐っている連中は何もしない。聖堂入り口、聖人像の下という場所柄もわきまえず、罰当たりも極まれりと言いたい。
聖堂前の広場には、「銅像」も立っていた。全身銀色の兵隊で、観光客が並んで写真を撮り、皿に小銭を入れる。銅像らしく見せるため身じろぎもしない。

これはそれなりの努力を要するもので、ただ坐っている連中とは大違いだ。私たちも撮った。妻が小銭を入れたが礼も言わない。銅像が礼を言ったらおかしなものだ。
広場の一角に古い時代のアーチ門のようなものが残っている。石を積んだだけのもので、よく崩れ落ちないものだと思うが、実は30年前、この門に腰掛けて写真を撮った。大聖堂周辺の駅や通りが記憶とかなり違っている中で、この門はまったく変わらず、ちょっとした感動を覚える。
そこで、よせばいいのに30年前と同じ位置に腰掛けて、娘に写真を撮ってもらった。
やはりよせばよかった。家に帰ったあと、前回の写真と今回の写真を並べてみて、歳月の残酷さに言葉もない。
しかし考えてみれば、30年前には自分がもう一度ここに来られるなどとは思いもしなかった。同一人物とは思えない2枚の写真を見比べながら、私はそれもいいかと思い直した。
こうなったら、また30年後に行ってやろう。今度はビールをちょっと控え目にして、神聖な場所にふさわしい態度をとろう。
南塔? もちろん登る。そのあとまた石造りのアーチ門に腰掛けて写真を撮るのだ。
| 「サウンド・オブ・ミュージック」ロケ地探訪 | |||