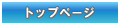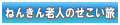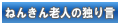不思議な国、エジプト(1)
貰う方が威張っている国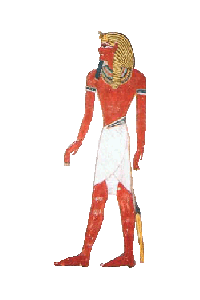
カイロに着いたのは、イスラム教のラマダン( 断食月 )が明けて間もない7月28日、午前6時過ぎであった。1982 年のことである。
ヘルメットをかぶり、剣つき鉄砲を担いだ兵士たちが見つめている。薄気味の悪い思いをしながら飛行機のタラップを降りた私は、到着ターミナルに足を踏み入れた途端、ギョッとして 思わず立ち止まってしまった。
狭くて汚いターミナルで、一見浮浪者・・・いや、二見しようと三見しようとやっぱり浮浪者にしか見えぬ男たちが、ざっと20~30人ほども、べったりと床に坐り込んで、こちらを見ているのである。
誰もが、ターバン( というよりは、ボロ布といった方が実感に近い )を頭に巻き、色も定かならぬ 汚れたガラベーヤをまとっている。
このガラベーヤというのは、エジプトの男たちの日常服で、防暑、防砂のためにはまことに具合が良い由であるが、見かけは何ともだらしなく、しかも清潔感に乏しい。
あとになって判ったことだが、彼らは外国に出稼ぎに行っていた者たちで、帰国はしたものの、読み書きができないので、入国手続きを係官に代行して貰うべく、じっと順番を待っていたものらしい。
ところが、その係官というのが どうやら まともな能力と責任感を持ち合せてはいないようで、私は今回の旅行中、各地の空港でずいぶんと腹立たしい思いをした。
この時も、私が入国書類に飛行機の寄港地を書き入れるためバーレーンの綴りを訊ねたところ、あろうことか、分らないという返事が返ってきた。
カイロに着く飛行機の多くがバーレーン経由の筈であるのに、入国審査官たる者がその綴りを知らないで、仕事になるものだろうか。
さらに、ビザを取ろうとすると、150 US$ をエジプトポンドに両替した証明書が必要だという。そんなことは聞いていなかったが、なにしろ相手は入国審査官であるから勝負にならず、銀行窓口で両替をして もう一度イミグレーションに行く。
ビザは貰えたが、そこでまた手数料を3ポンド取られる。
この旅行は 近畿日本ツーリストのパックツアーであり、添乗員は 山野井道子さんといった。 世界を股にかけて活躍している なかなかの女性で、私は後年、別のツアーでまたお世話になった。頼れる添乗員である。
その山野井さんが私の話を聞いて言うには、両替など必要なく、ビザ代の3ポンドだけでいいのだとのこと。そういうことは成田空港のロビーで山野井さんから詳しく説明されていたのだが、私は集合時間に1時間近く遅れて行ったため、このときまで何も知らなかった。
山野井さんも私はもう来ないと思ったらしく、既に参加メンバーを誘導して出国審査を済ませており、私との対面は機内であった。
幸い近畿日本ツーリストの社員がロビーで待っていてくれたので搭乗券を貰うことができたが、携帯電話などなかった頃であり、山野井さんも空席の筈の所に私が坐ったものだから、驚いたらしい。
バスに乗り、まずはカイロ博物館に行く。
 |
| ツタンカーメンの黄金のマスク |
古代エジプト文明というのは、世界の四大文明の中でもその華やかさにおいて群を抜いている。誰もが子供時代に強烈な印象とともに歴史への興味をかきたてられた経験を持つ、特異な文明である。
無論私もずっと関心を持ち続け、多少は勉強もした。
学生時代に東京の国立博物館でエジプト展が開かれたときには、押し合いへし合いしながらアラバスター(石花石膏)のカノピス容器など見て、ますますエジプト文明への憧憬を募らせもした。
勤務先の高校では「古代エジプト研究」なる講座を立ち上げ、生徒に古代エジプトのあれこれについて講釈しては、文化祭で発表などしてきた。
そんな私であるから、カイロ博物館はイスラム教徒にとってのメッカにも等しい聖地であり、長く眷恋し続けてきた場所である。
私は山野井さんに断って団体を離れ、かねてガイドブックで入念に調べておいた見学ポイントをじっくりと見て歩いた。
メンカウラー王群像は先述の東京での展覧会で見ている。ギザの三大ピラミッドの中で最も小さいピラミッドの主であるメンカウラーが左右に女神を従えて立っているその姿は、20年近い空白を感じさせない親近感をもって迫ってくる。
イクナトン王の立像は初めて見たが、その病的な顔つきと異様に膨らんだ腹部は既に写真で細部まで記憶しているそのままであり、興奮を抑えきれなかった。
と、背後から「アロー(矢)」と声をかけてきた者がいる。見ればミリタリー調の凛々しい制服を着た博物館員である。私が見入っていた物を、それは矢だと教えてくれたのであろう。
私は、そんなことは分っていると言うのも角が立つので、「フ・フン」とか言っておいたが、男はその後、私につきまとって次々に「アックス(斧)」だとか、「ジャー(壺)」だとか、分り切ったことを言い続ける。
私はその都度「 オー!」などと応じてはいたが、だんだん馬鹿々々しくなり、返事をしなくなっていった。
すると、男が「トキオ(東京)?」と訊いてきた。いや千葉だ、などと答えたところで分りはしないだろうから、イエスといい加減に答えた。
すると、私の返事にはまるで関係なく、「スーベニーア(土産)」と言う。一瞬何を言っているのか判らなかったが、手を出してきたので、この野郎!と思い、説明は頼んでいない、土産などない、と気色ばんだ。
しかし男は、アローだのアックスだのと単語で言う以上には英語が解らないらしく、「スーベニーア、ワンダラー」と繰り返している。小声であるところを見ると、さすがにそれが公務員として不適切な行為であることは分っているようだ。
そこで私はわざと大きな声で、この博物館では客から土産としてカネを取るのか と訊いた。それも通じなかったようだが、大声を出されてはまずいと思ったのか、男は無言で去っていった。
世界に冠たるカイロ博物館がなんたることか、と憤慨したが、あとになって、その男の振舞いはあれで比較的遠慮深いものだったのだと思うようになった。それについてはあとで述べる。
男を追い払ったあと、私はまたお目当ての展示物を見て歩いたが、その一つにアンケセナーメンの花束があった。
ハワード・カーターがツタンカーメンの墓を発見したとき、王の棺の胸の辺りに王妃アンケセナーメンが手向けた矢車草の花束が置いてあったという。
古代エジプト王としての強大な権力も持てぬまま18歳で死んだ悲運のツタンカーメン王に、妻が最後に捧げた花束、と聞けばなんともロマンチックで、世の夫たるものみな、かかる妻を持ちたいと思うのは当然であろう。
私は十分な予習をしてきている。館内のどこに何があるかは熟知していたから、いよいよその花束に近づいたとき、胸の高鳴りを抑えることができなかった。
そして、見た。
いったい、何ということであろう。清楚で小さな花束を想像していた私の目に飛び込んできたのは、長さ1メートル近く、太さはひと抱えほどもある干乾びた花束がデンと、それも2束置かれている光景であった。
こんなものを胸の上に置かれたのでは、死者はさぞかし息苦しかったであろうと思わざるを得ない。
私はしばし呆れた気分でツタンカーメンの死の場面を思い、そのあと、考えてみればそれもそうかな、と思った。
アンケセナーメンはアメンホテプ4世の娘である。
このアメンホテプ4世は、アメン神に仕える神官たちによって王権がないがしろにされてきたことに抗して、今後はアトン神を国神とするという宗教改革を行った。自らもアメンホテプ(アメンは満足する)という名をイクナトン(イクンアトン=アトンに愛される者)と変えるなどして意欲的ではあったが、虚弱な体質であったといわれ、32歳で病没している。
述べたとおり、その娘がアンケセナーメン(アンケス・エン・アメン)であるが、彼女は母ネフェルティティの後妻として父と結婚し、その死により、父の弟、すなわち叔父にあたるツタンカーメンと再婚した。そのとき13歳、相手は叔父とはいえ年下の9歳であった。
9歳といえば鼻たれ小僧である。アンケセナーメン自身はそろそろ大人の世界に興味も芽生える年頃で、政略結婚によって夫になったとはいえ、まだ子供々々したツタンカーメンに男として愛情を感じていたとは考えにくい。
ちなみに彼女はツタンカーメンの死後、アメンホテプの家臣であったアイと再々婚しており、やはり大人の男の方が魅力的だと感じていたことは想像に難くない。
それにツタンカーメンはアメンホテプ3世の子であるものの、母親がはっきりしないという具合で、あまり誇らしい血筋というわけでもない。
そんなわけであるから、アンケセナーメンは、ツタンカーメンが死んだとき内心せいせいして、葬儀に際しても侍女に花束を作らせ、さばさばとした気持でそれを棺の上に無造作に置いたのかも知れない。
そう思って見れば馬鹿でかい花束もなるほどと思え、それはそれでまたドラマチックと言えなくもない。
このツアーは実に良心的で、ツアーにありがちな土産物店巡りは全くなく、この博物館をはじめ行く先々の見どころでたっぷりと時間をかけた。だから学生時代に東京で見た秘宝との再会には、旧知の友人に会うような感激も覚え、彫像の細部まで記憶と照らし合わせる時間を取れた。
そんな満足感と興奮とをかみしめながら、次に向かったのはギザのピラミッドである。

バスを降りた途端、何人かの大人と子供に取り囲まれた。手に手になにやら土産物らしい物を持って、口々に何か叫んでいる。あとで落ち着いて考えると別に叫んでいた訳ではないのだが、その時は一瞬 強盗にでも囲まれたような気がして、おおいに慌てた。
逃げるように彼らの間をすり抜けて、ピラミッドの下に立つ。
なんという大きさであろう。
名所旧跡というものは、行ってみるとなんとも貧弱で、なんだこれは?というものが多い。世界三大がっかり名所とか、日本三大がっかり名所とかいう言葉があるくらいだから、多くの人が同じ思いを抱いているに違いない。
私に言わせれば、沖縄の守礼の門は世界でもまれに見るがっかり名所であり、あれほど陳腐な景観を旅情漂う絵葉書に仕立て上げるカメラマンの技には帽子を何回脱いでも敬意を表し切れない。
だから、ピラミッドにしても、実はそれほど期待していた訳ではない。エジプトのことを少しは勉強している以上、一度はこの目で見ておきたいという程度であった。しかし、この大きさは途方もなく、これなら 掛け値なく名所と言ってよい。
残念ながら砂漠のど真ん中にあるという訳ではなく、すぐ近くまでビル群は迫っているし、カメラの角度によってはホテルやレストランが写ってしまう。それでも、この大きさは予想を超え、真下から見上げた圧倒的な量感は 筆舌に尽くし難い。
山野井さんが、希望者は中に入っていいと言う。入るにはまた金を取られるのだが、そんなことはどうでもよい。
入口近くではただのオッチャン、アンチャンと思われる男たちが「ガイド、ガイド」と声をかけてくるが、無視。なにしろ私は内部の間取りがしっかりと頭に入っている。さながら、間取りを頭に叩き込んだ上で吉良邸に討ち入った赤穂浪士の如しで、内部のガイドはまったく必要としない。
盗掘孔から上昇通路、女王の間、大回廊等、写真で見ているとおりの空間を舐めるように確認しながら、最後に王の間と呼ばれる部屋に入る。
地上50メートルの高さにあるこの部屋、王の間とはいうが、それは後世の人間が勝手につけた呼び名で、実際の用途は判らない。
広さは畳にして30畳余り、東西に長い長方形で、全面花崗岩でできている。壁画、彫刻の類は一切なく、ただのガランドウである。端の欠けた 石棺のようなものが1個あるが、石棺にしては作りが粗末であり、第一、蓋がない。
まあ、このピラミッドについてはその複雑な内部構造について様々な説があり、それぞれの寸法を巡って、やれ黄金比がどうの、予言がどうのと喧しい。私もそういうことに多少の知識を持ってはいるが、確かなことは分らぬ。
そもそもエジプトについて詳しい人は星の数ほどいて、私などはシロウトの中のシロウト、そのまた中のドシロウトであるから、こんなところで中途半端な受け売りをひけらかすのはやめておこう。
それより私は、もっと単純な感慨に包まれていた。古代エジプト文明、ピラミッドといえば、誰もが子供の頃に限りない憧れを抱いたものであり、今自分がそのど真ん中に立っているというのは、ひょっとしたら事実ではないのかも知れないと思うほどの不思議であった。
であるから、私は確たる証拠に自分の写真を撮っておこうと思った。近くにいた人に頼んでカメラを渡し、石棺らしきもののそばに立った。
すると目の窪んだ、見るからにアラブ系の若い男が近づいてきて、私の横に立った。私は写真を撮るのでちょっとどけてくれと頼んだが、通じない。カメラを構えてくれた人にも、私一人を撮ってくれと頼んだが、それも通じない。
今その写真を見ると、その男はいかにも私の友人といった雰囲気で、にこやかにカメラを見つめている。 なんだか、私の長年の夢を台無しにされたような気分だ。
ピラミッドを出たあと、近くにあるスフィンクスを見に行く。胴体は長過ぎてバランスを欠き、造形的にも稚拙で迫力に乏しいが、頭部だけは素晴らしい。中世末期にイスラムの軍人によって故意に破壊されたということで、鼻などが欠損しているが、それが却ってこの正体不明の人面獅子像を謎めいた魅力で包んでいる。
私にとっては子供の頃の雑誌に連載されていた山川惣治の『少年王者』に出てくる怪人アメンホテップそのものであり、それを直接自分の目で見られる日がくるなどとは夢想だにしなかった異次元のモニュメントである。
夜、ホテルのティールームで ツアー参加者の懇談会のようなことが行われた。
メンバーは17人。いつもながら男は少なく、私を入れて4人。
1人で参加している初老の男性は、口数は少ないが好感の持てる人で、職業を問われると「百姓です」と言っていた。数日後、その人がこれまでにずいぶんと海外旅行をし、とりわけサマルカンドが良かったと言うのを聞いた。私はサマルカンドなどという地名が旅行先としてあがってくるその人に崇敬の念を抱いた。
女性陣はいつもどおりオバサンまたオバサンだが、その中に古賀さん、尾嶋さんという若い二人連れがいた。見た目は高校を出たばかりのようであったが、二人で毎年海外旅行をしているそうで、米、欧、豪といったメジャーな所は行き尽くし、今回目先を変えてエジプトに来たということ。
二人とも明るく、屈託がなく、可愛いので、たちまちツアーのマスコット的存在になった。ツアーで知り合った人はツアーが終わればそれ以上の付き合いはしないのが普通であるが、この二人とだけは別で、私はその後も行く先々から絵葉書を出し合ったりしていた。今も年賀状の交換をしている。
私は自己紹介で「見栄晴(みえはる)」と名乗った。ふざけて当時人気のタレントの名前を言っただけで、無論誰も本気にはしない。
古賀さん、尾嶋さんも笑いながら「見栄晴兄さん」などと呼んでくれたが、結局最後までそれで通し、その後の手紙も宛名は「見栄晴様」になっていた。住所が書いてあるとはいえ、それで配達してくれたのだから、郵便局も粋なものである。
メンフィス、サッカラ
翌朝、ホテルの前には土産物売りやヤミ両替屋が待ち構えていて、「トモダーチ」「コニチワ」などと声をかけてくる。それはどこの国でも同じで、無視してバスに乗る。
バスはまずメンフィスへ。
メンフィスで必見とされているアラバスター(雪花石膏)製のスフィンクスは、ギザのそれと違って端正な顔立ちが特徴であるが、風化が激しい上に野ざらしで、今後が心配になる。周囲に打ちこまれた4本の杭は傾いており、張られたロープも弛んで地面に接している。
誰でも触れるし、私も触ったが、こんなことでいいのだろうか。本気で文化財を保護しようという気があるのか、疑わしい。
歩いていると、道端にたむろする男たちがそれぞれ手を出して、何か要求するそぶりを見せる。無視して通り過ぎれば、それ以上のことはないのだが、あまり気持の良いものではない。
巨大なラムセスⅡ世像を展示してある建物に入る。展示物はこの像1体のみで、仰向けになっている。建物にはギャラリーがついていて、そこを歩きながら巨像を見下ろすことになる。
その巨像の脇に数人の男たちが腰掛けており、やはりしきりと手を差し出す。これも無視すれば、それ以上のことはない。
 |
| ラムセスⅡ世像 |
それはそれとして、このラムセスⅡ世像の立派なことには驚く。足の部分が欠損して全長12メートルほどになっているが、この像と対になって発見されたもう1体は現在カイロ市内のラムセス広場に立っており、それは15メートルある。
厚い胸板と太い腕、引き締まったウエスト、なによりも相当な美男である。
無論、実際のラムセスⅡ世がこんなに立派な容貌をしていたとは思えず、カイロ博物館に収められたミイラを見ても、鷲鼻で額の禿げ上がったひょろひょろの爺さんという感じでしかない。
しかし、古代エジプトでは歴代の王たちは皆、自分の像を立派に作らせているし、彫刻家たちも王の機嫌を損ねては大変と、今でいうなら写真屋が客のポートレートに修正を加えるようなことをしていたのだろうと思う。
それに、ラムセスⅡ世は67年間も王の座にあり、89歳まで、一説によれば92歳まで生きて、111 人の息子と69人の娘をもうけたと伝えられる大王である。自己顕示欲が強く、各地に自分の彫像を飾らせているが、どれもこれ以上はないという理想の体型をしている。
しばしその偉容に見とれ、その男ぶりに酔う。
そのあと建物の裏手に回ってみると、ナツメ椰子の茂みの中に、さほど大きくはないファラオの石像が転がっていた。半ば草に埋もれ、まるで大きなマネキンが捨てられているかのようなその扱いに、エジプト人はカネにならないものには冷淡なのかと、憤りを感じる。
バスに戻ろうとすると、途中でロバに乗った少女に出会った。頭にスカーフを巻いて、赤いワンピースを着ている。裸足だ。ロバの背に汚れた大きなポリタンクが括りつけられているところを見ると、水汲みに行くところなのかも知れない。

なかなか可愛い子だが、まったくの無表情で、黙って手を出す。こんな子供まで、と暗い気持になるが、可哀そうにもなり、50ピアストルをあげる。礼も言わず、無表情のまま去って行った。
そのあと、サッカラの階段ピラミッドを見に行く。古王国時代第3王朝のジョセル王のために造られた日干し煉瓦の墓で、拡張を繰り返して階段状になっている。
その設計者イムホテプは神官であり、宰相であり、建築家、医者としても優れ、ついには「知恵・医術・魔法の神」として神格化された。
その設計思想たるや現代にも通じる斬新なもので、階段ピラミッドも単なる墳墓ではなく、神殿や礼拝堂、葬祭殿を伴うコンプレックス(複合体)として造られた。
その遺構は今でも見事に残っており、古代エジプト文明に興味をもつ者にとっては、ある意味でギザのピラミッド以上に関心のある場所である。
無論、私も隅から隅まで貪欲に見て回った。写真も撮り、砂も採った。
まさにこれぞエジプト旅行という貴重な見学であったが、興醒めなことに、ここでも遺跡から一歩出た所では男たちが一斉に手を出し、何か話しかけてくる。
あとで判ったのだが、男たちは口々に「バクシーシ」と言っているのだった。
バクシーシというのは、日本語で言うと「施し」というようなことなのだろうか。イスラム教の道徳観では、富める者は富まざる者に富を分かち与えるのが当り前であり、貧しい者が豊かな者から金品を貰うことは、殆ど権利として認識されているらしい。
どうりで彼らは手を出すときに悪びれる様子がない。私から見れば、何だその態度は、と言いたくなるようなせびり方をする。
日本ではその昔、乞食というものがいて、道端に土下座して「右や左の旦那様、どうか哀れな年寄りにお恵みを」などと息も絶え絶えに恵みを乞うた。彼我の富の差、力の差を最大限に演出し、相手の優越感をくすぐって施しを受けようという、切なくも涙ぐましい努力をしたものである。
それがここエジプトでは、施しを受けようとする者たちがデカイ態度で、ときに命令口調で金品を要求する。こちらはおどおどして、彼らと目を合せないように足早に通り抜けなければならない。
といって、彼らはこちらが渡さない限り、力ずくで奪い取ったりはしない。旅行中、大男たちに取り囲まれて大声でバクシーシを要求される場面は何度もあったが、あとで考えてみると、体がぶつかることはあっても、金品をひったくられたことは一度もない。
あるときは「マネー、マネー」と言われ、ノーと言うと私の持ったボールペンを指して「ペン、ペン」と言われた。それもノーと言うと、今度は「カメラ、カメラ」と言う。冗談じゃない。
しかし、これもあとで考えてみると、彼らは厚かましく色々要求してはくるが、こちらが差し出さない限り、それに手を触れることはしない。
土産物売りも、こちらがよろけるほど体を密着させてつきまといはするが、ある線、たとえば入場券売り場の前までくると、拍子抜けするほどあっさりと諦め、別の観光客の方に走って行く。この辺の呼吸はなかなか呑み込めない。
市場など歩いていると、道端にしゃがんで世間話でもしているような男たちが次々にバクシーシをせがんでくる。無視すればそれ以上の要求はないので、まあ実害はないのだが、大の男がただ通りすがっただけの観光客に手を出してカネを貰おうとするその姿は、やはり感じの良いものではない。
あのメンフィスのラムセスⅡ世像の脇で手を出していた男たちも、おそらく近所のオヤジたちが暇つぶしがてら小遣い銭かせぎにやっているようなテイであった。ダメで元々、もし貰えれば儲けもの、というくらいの気持なのだろうが、いったい男のプライドというものはないのかと思ってしまう。
それに比べれば、あのカイロ博物館で「スーベニーア、ワンダラー」と金をせびった係員は、あれでも一応「矢」とか「壺」とか説明(?)して、その報酬を得ようとしただけマシなのかも知れない。