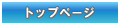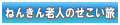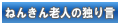「サウンド・オブ・ミュージック」ロケ地探訪
ドイツ在住の娘が遊びに来いと言うので、妻と出かけることにした。私はついでにオラン
ダを少し回ってから行こうと提案し、それに賛成した妻は、帰りにオーストリアに寄ろうと
言いだした。ザルツブルクで映画「サウンド・オブ・ミュージック」のロケ地を回りたいと
のこと。
私はあまり気乗りはしない。そもそもその映画を観ていないのだ。しかし、今回の旅は妻
を主役にと考えていたので、サービスのつもりで付き合うことにした。急遽映画の DVDを見
たが、画面の背景にばかり目がいって、ストーリーはあまり良く分らなかった。
私は、娘と別れたあとに妻と二人で行くつもりであったが、妻はいつの間にか娘とメール
のやりとりをして、3人で行くことになった。私だけでは頼りないと思ったのか、私とでは
退屈だと思ったのか、それは判らない。
しかし、結果として、それは大変良かった。
私はドイツ語が全く判らず、英語だって極めて怪しいものだが、まあ現地で国家天下を論
ずる訳ではないし、これまでにもドイツ、オーストリアは数回旅行しているから、何とでも
なると考えていた。それが行ってみると、どうにもならないことがすぐ分った。早い話がコ
インロッカーひとつ、自分では使えないのである。
娘の住むルートヴィヒスブルクからシュツットガルトで乗り換え、ザルツブルクまでの列
車行。まず切符の買い方が分らない。何番線からどこ行きに乗るのかも分らない。娘のあと
について列車に乗り込み、7時58分にシュツットガルトを出発した。
見ると通路を挟んで斜め前の席に、上半身裸の男が坐っている。ペーパータオルのような
ものを何枚も取り替えながら、しきりと体を拭いている。人目もはばからず、まあおおらか
なものだなと、我々は顔を見合せて笑った。電車が動き出してしばらくし、男はようやく汗
が引いたのか、次にテーブルの上に楽譜を広げ、指でキーボードを叩く仕草を始めた。とき
どき手を止め、考え込むようにして、また叩き出す。いつまでも裸で、いつまでも叩いてい
る。
やがて列車がアウグスブルクに着いた。男は慌ててシャツを着込み、鞄やら楽譜やらを小
脇に抱えると前のめりになって降りて行った。ホームを見ると、その男が楽しそうに一人笑
いをしながら歩いている。
ここで我々も声を上げて笑った。あの人は何なんだ?
12時09分、ザルツブルク着。暑い。ガラガラとスーツケースを押しながら、線路のガ
ードをくぐって駅裏に出、予約してあるホテルに向かう。
ホテルは4,5階建てだがフロントは民家の玄関ぐらいの広さで、2メートルもないカウ
ンターの中は人一人がやっと立てるほどしかない。呼ぶと、いかにも人の良さそうなおばさ
んが大声で「グーテンターク」と言いながら出てきた。私に判ったのはそれだけで、渡され
たキーの番号を頼りに階段を登る。エレベーターは、ない。
3階の部屋に入ると、そこは思いのほか広く、真ん中にテーブルと椅子、その奥にダブル
ベッドが1台とシングルベッドが2台ある。どれも量販店で売っているようなシンプルなも
ので、子供連れの家族が泊まるに適したような作りだ。
部屋の一角にシャワーボックスが置いてある。ホームセンターなどで売っている衣装ケー
スがガラスでできているだけのような、なんとも頼りないもので、しかも同室の者から丸見
えなので、これでは妻や娘が使うときには私は部屋にいられない。
まあ、それでも1人1泊朝食つきで20ユーロ、日本円にして 2,200円ほどであるから文
句は言えぬし、更に言えば、私は自分の青春時代の貧乏旅行を思い出し、まんざらでもなか
った。
何はともあれ、観光に出る。お目当てはヘルブルン宮殿。市街からは離れているのでタク
シーで行くが、見るからに一見の観光客といった態の我々であるから、料金をぼられる恐れ
は十分にある。事前に値段を確認すべし、と娘に厳命。私は言葉が判らぬので立っているだ
け。幸い予想額とメーターとがぴったり合い、チップを弾む。
ヘルブルン宮殿は水の宮殿とも呼ばれ、至る所に水を使った仕掛けがあって、大いに楽し
む。しかし、ここに来た目的はそれではなく、「サウンド・オブ・ミュージック」でトラッ
プ大佐とマリア、さらに長女リーズルとボーイフレンドのロルフが愛を語るシーンに使われ
た、ガラスのパビリオンを見ることだ。
ところがそれはなかなか見つからず、何人かに訊いたが分らない。やみくもに歩いている
と、ようやく見つかったが、それは実際に映画で使われたものではなく、映画ファンの強い
要望で再建されたものだとのこと。それでも映画の雰囲気は思い返せるので満足し、帰るこ
とにする。
映画で子供たちがサイクリングをしていた並木道で記念写真を撮ったりして、完全にミー
ハーと化した私はテンションが上がり、帰りのバスのキップを自分がドイツ語で買うと主張
した。ミラベル庭園まで3枚と言えばよい。平静を装いながら運転手に「ドライマル、ミラ
ベルガルテン!」と告げたが、思わず大声になってしまったのは悔やまれる。あとは運転手
が何を言ったかさっぱり判らぬまま切符と釣り銭を受け取り、市内に向かう。
途中、モーツァルト小橋の前を通ることが分かり、そこで下車。
映画で7人の子供たちが駆け渡る有名な橋で、ここでも妻と娘を歩かせてその様子を連写
。こうなるともう韓流ドラマのロケ地を回るオバサンたちとちっとも変らないが、幸いにも
、日本人だらけだと思っていたザルツブルクに日本人の姿は皆無といってよく、はしゃいで
いる我々を笑う人もいなかった。
映画で見覚えのある馬の噴水がある大聖堂広場を通って、高台のホーエンザルツブルク城
へ。市街を一望して城主の気分を味わっていると、前に来たことがあるという娘が城の最上
階を見学しようと言う。これには改めてチケットを買わねばならず、それはいいとしても、
売り場の係員は仲間同士で何やら喋っており、数人待っている客の方は一顧だにしない。
15分ほど待たされてようやくチケッ
トは買えたが、ここからはガイドについ
て歩くことになる。全く判らぬドイツ語
の説明を聞きながらの見学は退屈の限り
だが、それでも城壁の上に出ると、遠く
残雪をかぶった連山が望め、市街はさら
に手に取るように鳥瞰できる。これぞザ
ルツブルクという景観に大満足。
下りはケーブルカーでもよいのだが、
急ぐわけでもないので、歩いてノンベル
ク修道院に向かう。言わずと知れた、マ
リアが修行した修道院である。映画で子
供たちがマリアに会わせて欲しいと懇願する鉄格子の門はそのままであり、ここでも妻を立
たせて連写。しかし、そういうことに慣れていない妻はやはり映画のようなポーズはとれず
、結局はただ立っているだけで、連写の意味はない。
この日の最後はミラベル庭園。マリアと子供たちが「ドレミの歌」を歌いながら走り回る
きれいな庭で、映画そのままの門やら噴水やらに、またしても連写、連写。
ちなみにこのミラベル庭園には翌々日も行き、結果的に朝、昼、夕の三景を楽しんだが、昼間は団体の観光客が引きも切らず、写真を撮るのにも苦労する。
こうして映画の舞台を見て回り、映像と実景との重ね合わせに、時間も疲れも感じないで
楽しんでいたのだが、気がつくともう9時を過ぎている。なにせヨーロッパの6月は日が長
く、サマータイムを採用しているとはいえ、9時ではまだ夕方の明るさなのだ。
さすがに腹も減り、ザルツブルクで一番古いというビアホールに入る。中庭にしつらえた
テーブルにつくと、驚くべき早さで、若い太ったウエイターが注文をとりにくる。とりあえ
ずビールを頼み、料理の検討に入る。メニューが読めないので、娘が一つひとつ説明し、か
なりの時間を要する。外国人観光客の多いザルツブルクのこと、ドイツ語の読めない客も多
いだろうから、日本のように写真つきのメニューを用意すればいいものを、と娘に当たる。
ところが、ようやく料理が決まったというのに、頼んだビールは一向に来ない。見るとさ
いぜんのウエイターは汗を拭き吹き、首を振り振り客席の間を走り回っている。どうも客の
数は彼の処理能力を超えているようで、思い詰めたように走り回るその懸命な姿を見ると、
気の毒で催促するのもためらわれる。一度だけ声をかけると、「はい、ただいま」という意
味の返事をしたと思うのだが、やはり来ない。
ビールは注文を受けてから醸造するということもなかろうから、あれは単に忘れているの
だろうと話し合っていると、偶然そのウエイターと目が合った。彼はアッという表情で厨房
に消え、すぐさまビールを持ってきた。やはり忘れていたのだ。
料理が運ばれるまでにどれくらいの時間がかかったか、書くのもユーウツだが、それでも
味に申し分はなく、周囲の雰囲気もなごやかで、楽しい食事であった。
ただ、ホテルに帰ったときには玄関の鍵は閉まっており、予め渡されていた合鍵で入る始
末であったことだけは記録しておこう。
翌日は電車とバスを乗り継いでザルツカンマーグートのハルシュタット観光に出かけた。
これは丸一日かかったので、この日は「サウンド・オブ・ミュージック」のロケ地巡りは
せず、帰りに駅前のトルコ料理店で夕食をとった。
前日、妻と娘から「明日はお父さんの誕生日だね」と言われていたものだから、私は秘か
に豪華レストランでの高級ワインなど期待していたのだが、10時を回っており、開いてい
るレストランがない。この店も路上に出したテーブルだけでの営業で、それも横で椅子を片
づけたりしているのを見ながらピザとソーセージをつまむといった按配の、侘しいバースデ
ーディナーであった。
さてホテルのシャワーであるが、前述のとおり妻と娘が使う時間には、私は室内にいられ
ない。そこで、2階の廊下の隅にある共同のシャワー室に行った。初めに行ったときは中か
らシャワーの音が聞こえたので引き返し、2度目に行ったときは廊下で素っ裸の大男とぶつ
かりそうになり、慌てて部屋に戻った。
3度目は空いていたが、畳半分ほどの広さで脱衣所もなく、服を廊下の床に置いて中に入
る。天井にスプリンクラーと間違えるような蓮口があるが、手は届かない。前の壁になにや
ら黒いゴムの出っ張りのようなものが6個、金属のノブのようなものが2個ついている。あ
れこれいじっていると、突然、そのゴムから一斉に水が噴射され、同時に天井からシャワー
が降ってきた。それぞれが四方の壁に跳ね返って、何が何だか判らない。止めようとしたが
、どこをひねっても止まらず、しばらく食器洗い機の中にいるような状態が続いて、突然す
べてが止まった。
2晩目は、前夜の経験を生かし、シャワーが噴出されると同時にくるりと後ろを向き、首
を前に垂れてすべての攻撃に耐えた。両日とも体は洗わなかった。
3日目。朝食は前の朝とまったく同じメニューであった。3種類のチーズ、目玉焼き、ト
ースト、それにジュースとコーヒー。質素ながら実に美味しい、満足のゆく食事である。
運ぶのはチェックインのときに応対したおばさんで、愛想よく挨拶をしたあとは、厨房で
煙草を吸っている。黒のスパッツがなんとも場違いだが、まあ、いいだろう。私たちが滞在
している間、ほかに従業員らしい人は見かけなかった。
テーブルが4脚だけの狭い食堂にはアメリカ人と思われる老婦人の二人連れ、30代くら
いの母親と男の子。その母子にチーズの皿を運んできたおばさんが、うっかり皿を床に落と
し、皿は無論割れた。おばさんはオーッ、オーッとか言いながら、そのくせ平然と皿を片づ
け、瞬時にしてまったく同じ盛り付けのチーズを持ってきた。その日の宿泊客の分は予め盛
ってあり、まだ食堂に来ない客の分を持ってきたのだろう。
1日に何組もない客である。次の客には、床から拾ったチーズが出されるのではなかろう
か。
この日は午後フランクフルトまで電車で移動することになっているので、荷物を持ってホ
テルを出た。駅のコインロッカーに荷物を預け、サウンド・オブ・ミュージックのロケ地巡
りを続ける。
まず向かったのはメンフィスベルクの展望台。映画でマリアと子供たちが歌いながら歩く
シーンに使われている。展望台に上がるエレベーターの切符は娘に買ってもらったが、入ろ
うとすると回転バーが動かない。チケットのバーコードを機械に読み取らせるのだが、どう
かざしても反応がない。はてなと思ってチケット裏の説明を見るが、これがドイツ語で、ど
うにもならない。あれこれやってやっと動いたが、なぜか妻はすんなり通っており、どうも
メンツを潰された気分だ。
映画のシーンとまったく同じ場所に立っ
て、「ここだ、ここだ!」とはしゃいでい
た私は、娘に乗せられて映画の長男フリー
ドリッヒのポーズをとった。あとで送られ
てきた写真を見ると、白髪頭の短足爺さん
が歯をむき出して上を向いている。やはり、ああいうことはすべきでない。
映画に出てきた馬洗い池という所に行く。広い場所だと思っていたその池は、意外にも道
路のわきにあるこじんまりとしたもので、ローマのトレビの泉を見たときのような、軽い失
望感をもった。しかし、こういう何の実利性もない空間をずっと保持しているのがヨーロッ
パのヨーロッパたるところで、日本では望むべくもないであろう。
最後に、映画でトラップ一家がナチの追手から逃れるために隠れた、ザンクト・ペーター寺院の墓地を訪ねる。映画では石畳の広場だった所は墓石の並ぶ草地で、子供たちが隠れた鉄格子内の空間も、実際にはない。映画の場面を彷彿とさせるのは鉄格子だけで、その鉄格子の中には等身大の骸骨像と墓石がある。日本では骸骨というと気味悪いものであるが、こちらでは死者を偲ぶよすがとなっているのであろうか。
かくして「サウンド・オブ・ミュージック」のロケ地巡りを終え、午後、娘と別れてフランクフルトに向かったが、実は、ザルツブルクにはもう一つの顔がある。モーツァルトが生まれ、活躍した地ということで、町中、モーツァルトにまつわる見どころが散在している。私たちもいくつか回り、写真を撮ったりした。
しかし、実のところ、私はモーツァルトには何の興味もない。小学生か中学生の頃に「交
響曲第○○番○短調」の作曲者とか聞いたような気もするが、何のことやら分らない。
だから、ザルツブルクに行ったことで「じゃあ、モーツァルトの生家に行った?」と興奮
気味に訊かれても、「ああ、行ったよ」というぐらいしか答えられない。
ただ、今回の旅で、ザルツブルクがモーツァルトの町であることだけは、しっかりと覚え
た。その理由はこうである。
ホテルにチェックインしたとき、おばさんが愛想よくチョコレートを3粒くれた。各粒が
モーツァルトの肖像入り包装紙でくるまれたもので、私は、こんなところにもモーツァルト
か、と軽く思っただけで忘れていた。
それを夜になってふっと思い出し、「あのチョコレート、食べてみようか」と言った。す
ると妻と娘が目を丸くして顔を見合わせ、「食べちゃいましたよ!」と叫ぶなり、床に倒れ
込んで笑い転げている。
どうやら、私がシャワーに行っている間に2人で食べ、娘がこれお父さんの分、と言った
のを、妻が、「お父さんは食べないよ」と言って2人で割って食べてしまったらしい。
確かに私は普段チョコレートなど食べはしない。おばさんがくれたときにも自分が食べる
とは思いもしなかった。食べてみようか、と言ったのは旅の非日常性の中での、ほんの気紛
れであり、それが食べられなかったからといって、どうということはない。
しかし、あの母娘の笑い転げようは尋常ではなく、俺とチョコレートとはそんなにミスマ
ッチなのかと自問してしまった。
そして翌日も翌々日も、町中のいたる所でそのチョコレートを売っているのがやたら目に
つき、ザルツブルクと言えばチョコレート、チョコレートと言えばモーツァルト、という図
式が私の頭の中ででき上がってしまったのである。
== 2010年6月に出かけた旅の1頁です ==
| 二日酔いを反省、荘厳なミサ |