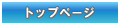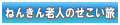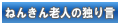楊貴妃考
愚帝に狂わされた人生
世界の三大美女という言い方を聞いたことがある。
古代エジプト最後の女王クレオパトラ、中国唐代の皇帝の寵姫楊貴妃、そして日本の平安時代の女流歌人小野小町であるという。
前二者の生涯が数々のロマンスに彩られ、官能的な匂いに満ちているのに比べ、小野小町の方はどうも艶っぽさに欠ける。○○なし小町などと揶揄されたのでは、オリエントの妖花たちに並ぶべくもない。
傾国の美女という形容も、わが小町殿には無縁である。その点、クレオパトラは、シーザー、アントニウスという傑出した2人の武人を翻弄して、あのローマ帝国をまさに傾けさせてしまった。さらに楊貴妃は、時の皇帝を腑抜けにしてしまった上、一族の栄達を画し、もって内乱の原因を作ってしまったのだから、文字通り傾城傾国の美女ということになろう。
楊貴妃。8世紀初め、蜀州の下級役人楊玄淡の子として生まれた彼女は、名を玉環といった。幼くして父母に死別し、叔父に育てられたが、豊麗な美女に成長すると、17歳で玄宗皇帝の第18皇子、寿王の妃となった。
そのころ唐は、第8代皇帝玄宗の治下にあった。
玄宗は28歳で皇位につき、世に開元の治といわれる積極的な政治を展開したが、長い治世で次第に政治に飽きてきたらしい。そんなとき、皇后武恵妃が世を去る。
玄宗は武恵妃の代わりを求める。彼のハーレムには「後宮の佳麗三千人」といわれた美女たちがはべり、まさにより取り見取りであった。しかし、それまで美女という美女を恣にしてきた玄宗にとって、武恵妃なきあとの無聊を慰めるに足る女はいなかった。というより、ハーレムの女たちでは新鮮味がなかったということかも知れない。
彼は、側近の高力士に命じて宮廷内外に美女を探させた。高力士は、こともあろうに楊玉環に白羽の矢を立てる。
時代とはいえ、皇帝とはいえ、そして他に前例があったとはいえ、息子の嫁を父が奪うというのは、さすがに品の良い話ではない。そこで玄宗は、姑息な手を用いた。
玉環を出家させ、いったん“夫のいない女”にしてから、自分の後宮に入れたのである。ときに玄宗60歳、玉環は26歳という若さであった。
ただ断っておくならば、当時の記録、伝承はそのすべてが矛盾なく整っているわけではなく、私がこの稿でとっている数字もすべてが正確だとは言い難い。げんにこの時の両者の年齢も55歳、22歳という資料もあるし、寿王は玄宗第9皇子という資料もある。だいたい玄宗の皇位からして、第8代というが、これもそれ以前に重祚した2人の皇帝を2度ずつ数えてのことであり、それを除いて6代と呼んでいる歴史家もいる。なんだかよく分からないが、まあ、どうでもよい。
それはともかく、この後宮というのは前述したように、いわばハーレムで、6つに分れ計3千人の美女がはべっていたという。
3千人とはまた途方もない数で、誇張分を差し引いたとしても、とても玄宗1人の手におえる数ではない。一度も声のかからぬまま役目を終えた女も相当いたであろう。それでいながら、女達が他の男と通じるのを防ぐため、後宮に近づき得る上級役人をことごとく去勢したというのだから、げに権力とは勝手なものである。
さて、この後宮に入った楊玉環の美しさは大変なもので、白居易の『長恨歌』によれば、「眸を廻らして一笑すれば百媚生じ、六宮の粉黛顔色なし」と詠われている。
その玉環が初めて玄宗の伽を務めるにあたり、華清池の温泉で身体を洗うことになった。「温泉水滑らかにして凝脂を洗う。侍児扶け起こせば嬌として力無し。始し是れ、新めて恩澤を承けなん時ぞ」
 |
| 楊貴妃像 |
あまり今日的なエロティシズムとは言えぬが、ただならぬ艶めかしさがあったであろうとは想像できる。
60歳といえば、男女のことに多くの時間を残しているとは言えぬ。玄宗は、この眩しいばかりの豊艶の美女を手に入れると、以後、政治向きのことは宰相任せにして、一刻を惜しむように、ただただ玉環の色香に酔いしれて日々を過ごすことになる。
それにしても、玉環に後宮の最高位、即ち皇后に次ぐ「貴妃」という称号を与えて「楊貴妃」としたのはいささか理性を欠いた軽挙と言わざるを得ない。その上、その楊貴妃の衣服を作るためだけに700人の仕立て職人を雇っていたというのだから呆れる。
さらに貴妃の好物であった茘枝をしばしば買い与えたなどは、女子高校生に服など買ってやって必死に歓心を買おうとする現代の中年男を見るようで、哀れでさえある。なにしろ茘枝といえば高価なばかりでなく傷みやすい果物で、しかも産地は長安から遠く直線距離にして1200キロも離れた広東省である。今日のように冷蔵庫やクール宅急便がある時代ではない。食べる量だけを、その都度早馬で運ばせることになる。誰が見ても小娘に鼻毛を読まれてヤニさがっている態であり、皇帝たる対面も何もあらばこそ。ひと事ながら、しっかりしろと言いたくなる。
もっとも、この手の話、なにも玄宗に限らぬ。地位、財力の違いからどうしても話は小振りになるが、私達の周りでも若い女の子に媚を売られ、節操もなくその機嫌を取ろうと立ち回る中年男の姿を見ぬ日はない。
困ったことに、女達の中には正義よりも己の利益を優先する者がいて、“自分に対してよくしてくれる男”であれば、たとえそのために男が不正義を働こうと気に止めない。女にとって“都合のいい男”が結局は“いい人”であって、そういう節度のない男により多くの女が近寄ってくるという現実がある。
この辺については具体的な例を挙げて詳述しないと解りにくいのだが、例を挙げたらたちまち何人かに差し障りが生ずるので、解りにくいのを承知で抽象的な言い方にとどめておく。
さてそれでは楊貴妃が玄宗皇帝を“いい人”だと思って身も心も捧げていたのかというと、それはどうであろうか。
普通に考えれば、若い人妻が突然生木を裂くように夫と別れさせられ、会ったこともない権力者、それも夫の父親の伽の相手を命じられて喜ぶとは思えない。仮に一歩譲って、その女がうだつの上がらぬ夫に飽きていて、権力者の下での華やかな生活にあこがれていたとしても、だからと言って連夜60歳の男にその身を呈することが心を焦がすほどの愉悦であろう筈もない。
私の無責任な憶測を言うならば、楊貴妃は“都合のいい男”をそのまま“いい人”だと思うほど馬鹿な女ではなく、それどころか、どのみち避けられぬ運命ならば、天賦の美貌を利して最大の利益を上げようという、したたかな女だったのではないか。それが言い過ぎなら、抗い難い運命に弄ばれながら、せめて我が身を犠牲に一族の繁栄を図ろうとした薄幸の女というところでどうであろう。
腹を決めた楊貴妃は、玄宗皇帝にしなだれかかり、次々とねだり事をしていった。玄宗はそれに応え、楊一族の者を次々と要職に就かせる。又従兄の楊国忠もその一人だが、もともと酒と博打にうつつを抜かし、調子の良さだけで立ち回っていた国忠は人望もなく、やがて節度使の安禄山と対立する。安禄山は楊一族にとって極めて不都合な、いわば獅子身中の虫とも言うべき存在であったが、実は楊貴妃はその安禄山と密通していた節もあり、どうしてなかなかの女である。
すっかりまつりごとに意を用いなくなった玄宗をよそに楊一族が政治を私物化。当然世の中は乱れる。世を憂えたか、機を見たか、はたまた日頃の対立から身の危険を感じたか、安禄山は史思明と組んでクーデターを起こす。世に言う安史の乱である。
楊貴妃のコネで成り上がっただけの楊国忠が、もともと武人として身を立ててきた安禄山に勝てるわけもなく、楊国忠は玄宗、楊貴妃を伴い蜀地方に逃走する。玄宗はいわば楯として使われたわけで、ときの皇帝としてはいかにも情けない。
ところが、その逃避行のさなか、疲労と飢えに苦しんだ将兵が、安禄山の挙兵を招いた責任者として国忠を暗殺する。さらに将兵は諸悪の根源は楊一族の専横を招いた楊貴妃にありとして、玄宗に貴妃の処刑を要求、玄宗は抗し切れず、高力士に命じて貴妃に首を吊らせた。ときに楊貴妃、37歳であったという。
玄宗はその後ウジウジと楊貴妃を思い、彼女の絵を毎夕眺めていたということで、白居易の『長恨歌』には玄宗がいかに彼女に心を奪われていたかが綿々と綴られている。まあ、なんともいただけない男である。
かく見てみると、私には楊貴妃が心から玄宗を愛していたとはとうてい思えない。
抗う術もない権力者の命にやむなく従いながら、内心ではさげすみ、嫌悪し、せめてそれを利用しようと偽りの愛を捧げた。そのやるせなさの中で、安禄山との密通に一瞬の安らぎを求めたが、皮肉にも自分がお膳立てした一族の栄達が安禄山との対立を招くことになる。
玄宗、楊国忠、安禄山。意のままに操れた筈の三者がそれぞれ楊貴妃の望まぬ争いに走り、あげくは尻尾を巻いて逃げる玄宗に連れられ山中をさまよい、ついには部下の圧力に屈した玄宗の命により、若い命を絶たれた。
世界に冠たる大帝国の皇帝との華やかなロマンスに包まれた絶世の美女というイメージで語られることの多い楊貴妃。それをぶち壊して喜ぶつもりはない。
ただ、私はそういう華やかな女としての楊貴妃よりも、たぐいまれな美しさゆえに心ならずも平凡な人生を断ち切られた女としての楊貴妃の方が強く心に響く。
つまり、夫から自分を奪った皇帝に嬉々として色香を捧げた女ではなく、その運命を一族のために生かすべくしたたかに身を呈し、結果、せっかく盛り上げた一族と共に自らをも滅ぼすことになった幸せ薄い女、という色づけこそが、私の抱く楊貴妃像である。
| この言葉、なんとかなりませんか(4) | 情けない「○○甲子園」 | ||